注目判例&新法情報
一覧
【注目判例】 再転相続人の熟慮期間の起算点について :最高裁第2小法廷R1.8.9判決
 事案の概要
事案の概要
甲銀行は,乙会社に貸金等の返還を求めるにあたり,乙社の貸金等返還債務の連帯保証人となっていたA(X2の叔父)らに対し,連帯保証債務の履行として8000万円の支払いを求める訴訟を提起し,平成24年6月7日,甲の請求を認容する判決が言い渡され,その後,この判決は確定しました。判決言渡し直後の同月30日,Aが死亡し,相続人であったAの妻,子2人は,同年9月までに家庭裁判所に相続放棄の申述をして受理されました。この結果,Aの兄弟姉妹およびその代襲相続人(亡くなった兄妹姉妹の子)の合計11名がAの法定相続人となったのですが,このうちB(Aの弟でX2の父親)は,平成24年10月19日,自分がAの相続人となったことを知らないまま,したがって,相続の承認あるいは放棄の手続をとらないまま,死亡してしまいました。Bの法定相続人は,妻X1と二人の子(X2ほか1名)です。
甲銀行から平成27年6月に上記の確定判決にかかる債権を譲り受けたY社は,同年11月,X1,X2について,その相続分の範囲で強制執行することができる旨の承継執行文の付与を受け,これが同月11日,X2に送達されて,X2は初めて父BがAの相続人になっていたこと,自分がBからAの相続人としての地位を承継していたことを知りました。さらに,Y社は,平成28年1月12日,Bが所有していた不動産について相続による所有権移転登記を代位により経由した後,この不動産について強制競売の申し立てを行いました。そこで,X2は,X1とともに,平成28年2月5日,Aからの相続について家庭裁判所に相続放棄の申述を行い(同月12日にこの申述は受理),さらに,同月23日,相続放棄をしたことを異議事由として,Y社の強制執行を許可しないことを求める「執行文付与に対する異議の訴え」(民事執行法34条)を提起しました(なお,X1は,第1審で相続放棄の再抗弁を撤回しています)。
原審は,“再転相続”が生じた場合の再転相続人の熟慮期間を定めた民法916条の「その者の相続人が自己のために相続の開始があったことを知ったとき」について,相続の承認又は放棄をすることができる状態であること,すなわち,第一相続(*本件ではAの相続)が開始したことを知っていることを前提としていると読むべきであり,第一相続の相続人(*本件ではB)が自己のために第一相続が開始していることを知らずに死亡した場合は,民法916条はそもそも適用されず,第一相続の相続人としての地位を包括承継した再転相続人(*本件ではX1,X2)が,民法915条の規定に則り,第一相続についての承認又は放棄をすれば足りるとし,本件の場合,Aの相続(第一相続)に関するX2の熟慮期間は,X2が父BからAの相続人ついての地位を承継した事実を知った時から起算され,本件相続放棄は熟慮期間内にされたものとして有効となると判断しました(大阪高等裁判所・平成30年6月15日判決)。
今回は,Y社の上告について最高裁が示した判断を紹介します。
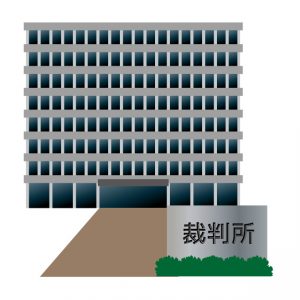
裁判所の判断
〇 熟慮期間の起算点である「自己のために相続の開始があったことを知った時」(民法915条)の解釈
相続人は,自己が被相続人の相続人となったことを知らなければ、当該被相続人からの相続について承認又は放棄のいずれかを選択することはできないのであるから,民法 915 条 1 項本文が熟慮期間の起算点として定める『自己のために相続の開始があったことを知った時』とは,原則として,相続人が相続開始の原因たる事実及びこれにより自己が相続人となった事実を知った時をいうものと解される(最高裁昭和57 年(オ)第82 号同 59 年 4 月 27 日第二小法廷判決・民集 38巻 6 号 698 頁参照)。
〇 再転相続人の熟慮期間を定めた民法916条の趣旨
民法 916 条の趣旨は,「BがAからの相続について承認又は放棄をしないで死亡したときには,BからAの相続人としての地位を承継したX2において,Aからの相続について承認又は放棄のいずれかを選択する ことになるという点に鑑みて,X2の認識に基づき,Aからの相続に係るX2の熟慮期間の起算点を定めることによって,X2に対し,Aからの相続について承認又は放棄のいずれかを選択する機会を保障すること」にあるのであり,「X2 のためにBからの相続が開始したことを知ったことをもって,Aからの相続に係る熟慮期間が起算されるとすることは,X2に対し,Aからの相続について承認又は放棄のいずれかを選択する機会を保障する民法 916 条の趣旨に反する。」
〇 民法916条の「その者の相続人が自己のために相続の開始があったことを知ったとき」の解釈
以上によれば,「民法 916 条にいう『その者の相続人が自己のために相続の開始があったことを知った時』とは,相続の承認又は放棄をしないで死亡した者の相続人が,当該死亡した者からの相続により,当該死亡した者が承認又は放棄をしなかった相続における相続人としての地位を,自己が承継した事実を知った時をいうものと解すべきである。」
なお,最高裁は,原審・大阪高裁が民法916条が適用される場面をBにおいて自己がAの相続人であることを知っていた場合に限定した点については,「Bにおいて自己がAの相続人であることを知っていたか否かにかかわらず民法 916 条が適用されることは,同条がその適用がある場 面につき,『相続人が相続の承認又は放棄をしな いで死亡したとき』とのみ規定していること及び 同条の前記趣旨から明らか」であるとして,原審の判断には民法 916 条の解釈適用を誤った違法があると指摘しています(本件の相続放棄が熟慮期間内にされたものとして有効との結論は是認)。

解 説
◇ 相続の承認,放棄と「熟慮期間」
人が亡くなると自動的に相続が開始します。相続とは亡くなった人(被相続人)の財産,権利・義務の一切を引き継ぐことを言い,財産にはプラスの財産だけではなくマイナスの財産 (負債)も含まれるので,負債を多く抱えていた人を必ず相続しなければならないとしてしまうと,相続人としては他人の死という自分ではコントロールできないことによって非常に酷な状態に置かれてしまうことになってしまいます。このため,民法は,相続人に相続を承認するか放棄するかの選択権を認めています。この相続を承認するか,それとも放棄するかを選択する期間について,民法915条1項は,「相続人は,自己のために相続の開始があったことを知った時から3箇月以内に,相続について,単純若しくは限定の承認又は放棄をしなければならない」と規定しています。この3ヶ月を相続の熟慮期間と言います。3ヵ月という短い期間ではどうしても選択できないという場合には,家庭裁判所の許可が必要になりますが,熟慮期間を伸長することも認められています(同項但書)。
熟慮期間の起算点は,条文では「自己のために相続の開始があったことを知った時」となっており(915条1項),最高裁判例においても,原則として,「相続人が相続開始の原因たる事実及びこれにより自己が相続人となった事実を知った時から起算すべきもの」とされています(本件判決が引用する最高裁第2小法廷昭和 59 年 4 月 27 日判決・民集 38巻 6 号 698頁)。ただ,この最高裁判例は,「相続人が右各事実を知った場合であっても,右各事実を知った時から 3 か月以内に限定承認又は相続放棄をしなかったのが,被相続人に相続財産 が全く存在しないと信じたためであり,かつ,被相続人の生活歴,被相続人と相続人との間の交際状態その他諸般の状況からみて当該相続人に対し相続財産の有無の調査を期待することが著しく困難な事情があって,相続人において右のように信ずるについて相当な理由が認められるとき」には,例外として,「相続人が相続財産の全部又は一部の存在を認識した時又は通常これを認識しうべき時」から起算するのが相当としています。亡くなった人に相続財産がないと信じることについて無理からぬ事情がある場合に限って,3ヶ月を徒過してしまっても,相続放棄の機会を認めている訳です。
◇ 「再転相続」とは?
本件では「再転相続(さいてんそうぞく)」が生じた場合の熟慮期間の起算点が問題となっています。「再転相続」とは,ある相続(一次相続)が開始した後,その相続人が相続の承認または放棄をしないまま死亡し,二次相続も開始したケースにおける二次相続の相続人による一次相続の相続のことをいいます。本件では,X1,X2らがAの相続についての再転相続人ということになります。
再転相続人からみると,承認または放棄の選択をする対象となる相続が2つ(第一相続と第二相続)あることになります。この点について,再転相続人の第一相続に関する選択権は第一相続の相続人から引き継がれるものではなく再転相続人の固有の権利であるとして,再転相続人は,第一相続,第二相続とも,順序に関係なく承認・放棄を自由にできるとする見解もありますが,最高裁昭和63年6月21日判決は,再転相続人は第一相続,第二相続のそれぞれについて承認・放棄を格別に選択することができるが,先に第二相続を放棄した場合には,再転相続人は第一相続の相続人の権利義務を何ら承継しなくなるとして,第一相続についての選択権も失うことになるとしています(この最高裁の考え方によれば,先に第一相続を承認し,後から第二相続を放棄することは可能ということになります)。
本件では,X1,X2らは,第二相続(Bの相続)について相続放棄の手続を採っていないので,第一相続(Aの相続)について承認・放棄の選択をすることは順序の点からは問題とはならず,3ヶ月の熟慮期間をどこから起算すべきかが争われました。
◇ 「再転相続」における第一相続の熟慮期間の起算点
再転相続が生じた場合の熟慮期間の起算点については,民法915条1項の特則として916条が設けられており,「相続人が相続の承認又は放棄をしないで死亡したときは,前条第1項の期間は,その者の相続人が自己のために相続の開始があったことを知った時から起算する」と規定されています。「その者の相続人」が再転相続人(本件のX2ら)を指すことは明らかですが,「自己のために相続の開始があったことを知った」という対象となるのは第二相続のことなのか,それとも第一相続のことなのかに争いがありました。
原審の大阪高裁は,前者の立場,すなわちX2が第二相続(Bの相続)の開始があったことを知った時から第一相続の熟慮期間も原則として起算されるとした上で,例外として,第一相続の相続人(B)が第一相続の相続人となったことを知らずに死亡した場合には916条は適用されず,915条の規定に則り,「自己のために相続の開始があったことを知った時」から第一相続の熟慮期間を起算すればよいと判断しました。第二相続の開始を知った時から第一相続の熟慮期間も起算されるという見解は,実は従前の通説的見解であったようです。しかし,この見解に立つと,本件のように第一相続の被相続人Aとの関係が疎遠な人が再転相続人となるケースにおいては,再転相続人が全く予想できない形で負債を相続してしまうリスクも出てきます。原審の大阪高裁判決は,こうした不都合を916条の適用場面を限定することによって解消しようとした訳ですが,本最高裁判決は,第一相続の相続人が第一相続の相続人となったことを知っていた場合に916条の適用場面を限定するという解釈は条文の文言及び916条の規定の趣旨から取り得ないと大阪高裁の見解を退けた上で,再転相続人(X2)が「当該死亡した者(=B)からの相続により,当該死亡した者が承認又は放棄をしなかった相続(=Aの相続)における相続人としての地位を,自己が承継した事実を知った時」を熟慮期間の起算点とすることにより,再転相続人の選択の機会を保障したのです。
 コメント
コメント
本判決は再転相続における熟慮期間の起算点を規定する民法916条の解釈を示した初めての最高裁判決として注目されました。核家族化,そして少子化が進展している現代では,疎遠になっている親族の相続人となるケースは決して珍しくないと思われます。その場合,債務を抱えていた人の相続人となったことを知った時から3ヵ月の熟慮期間が起算され,その間に相続放棄をすれば債務を引き継がなくてすむことが今回の判決により明確になりました。今後の債権回収の実務等にも影響があるものと思います。
【注目判例】 マンション管理組合総会における高圧一括受電方式導入決議の効力が否定された事案:最高裁H31.3.5判決
 事案の概要
事案の概要
〇〇マンション(区分所有建物4棟,総戸数544戸。「建物の区分所有等に関する法律」は,一団地内に数棟の建物がある場合,“団地”,“団地管理組合法人”と呼ぶのですが〔65条以下〕,ここでは便宜上,“マンション”,“管理組合法人”としておきます。)では,従来,各区分所有者は,各自の専有部分において使用する電力の供給契約をA電力会社との間で個別に締結していました。電力の供給は,マンションの共用部分に設置された配電設備を通じて行われていました。
マンションの管理組合法人(Z)は,区分所有者の専有部分の電気料金の削減を図るため,平成26年8月の通常総会において,Zが一括してA社との間で高圧電力の供給契約を締結し,各区分所有者はZとの間で各自の専有部分において使用する電力の供給契約を締結するいわゆる一括高圧受電方式へと変更する旨の特別多数決議を行いました(以下,本件決議と言います)。その後,高圧受電方式に変更するためには,A社と個別契約を締結している区分所有者全員がその解約手続を行う必要があったため,平成27年1月の臨時総会で,高圧受電方式以外の方法により電力の供給を受けてはならないことを規定する「電気供給規則」を新たに制定する旨の特別多数決議を行いました(以下,この決議に従って制定された規則を本件細則と言います)。Zは,これらの決議及び本件細則に基づき,区分所有者全員に対し,A社との個別契約の解約申し入れに係る書面の提出を求めたのですが,Yら2名はこの書面をZに提出せず,また,A社に対しても個別契約の解約申入れをしませんでした。この結果,〇〇マンションでは高圧受電方式への変更ができなくなり,Zは,平成28年8月の総会で,高圧受電方式の導入を保留する特別多数決議を行うことになりました。
このような状況において,Zが設置した専門委員会の一員として高圧受電方式の導入に向けて奔走したXは,A社との個別契約の解約申入れをすべきとする総会決議,本件細則に基づく義務にYらが違反したため,高圧受電方式への変更が実現せず,その結果,専有部分の電気料金が削減されないという不利益・損害を被ったと主張し,Yらを被告として損害賠償を求める訴えを提起しました。Yらは,電力などライフラインの供給元の選択は,専有部分の区分所有者が自由に決することができる事項であって,本件決議は,区分所有権の本質的事項にかかわるものとして法的拘束力がない等と反論しました。
1審の札幌地方裁判所は,Yらが主張したライフライン供給元の選択の自由について,「区分所有建物にあって,電力会社から受ける電力は全体共用部分,各棟共用部分を通じて専有部分に供給されるものであるから,電力の供給元の選択においても,共同利用関係による制約を当然受けるものである」と判示し,本件決議等により設定された義務にYが違反したことによってXには高圧受電方式による低廉な電気料金という利益を享受できなくなるという損害が生じているとして,Xの請求を一部認容しました(H29.5.24判決)。控訴審においても第1審の判決が維持されたため(札幌高裁H29.11.9判決),Yらが最高裁に上告したというのが本件の経過となります。今回は,Yらの上告について最高裁が示した判断を紹介します。
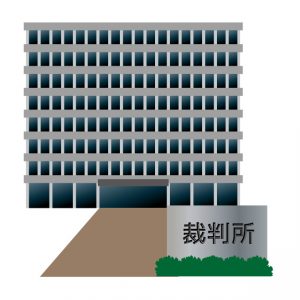
裁判所の判断
○ 本件決議は「共用部分の変更又はその管理に関する事項」を決するものとして効力を認めてよいか
本件決議の効力を否定。
「本件高圧受電方式への変更をすることとした本件決議には,団地共用部分の変更又はその管理に関する事項を決する部分があるものの,本件決議のうち,団地建物所有権者等に個別契約の解約申入れを義務付ける部分は,専有部分の使用に関する事項を決するものであって,団地共用部分の変更又はその管理に関する事項を決するものではない。したがって,本件決議の上記部分は,法17条1項又は18条1項の決議として効力を有するものとはいえない」
○ 本件細則は「建物所有権者相互間の事項」を定めたものとして効力を認めてよいか
本件細則について「建物所有権者相互間の事項」を定めた規約としての効力を否定
「本件細則が,本件高圧受電方式への変更をするために団地建物所有者等に個別契約の解約申入れを義務付ける部分を含むとしても,その部分は,法30条1項の『建物所有者間相互間の事項』を定めたものではなく,同項の規約として効力を有するものとはいえない」

解 説
◇ マンション共用部分の「管理」「変更」
民法上,管理行為(広義)とは,財産を現状において維持し(=保存行為),また,財産の性質を変更しない範囲で利用・改良を目的とする行為(=狭義の管理行為)とされています。マンション共用部分の管理として考えてみると,共用部分の清掃,損壊部分の修繕などは保存行為,共用部分の駐車場を貸して賃料収入を得ることは利用行為,共用部分に設置された電灯をLEDに変更するような行為は改良行為ということになります。以上の管理行為(広義)に対して,財産の性質・形状の一方または両方を変えることを変更行為と言います。マンション共用部分で考えてみると,エレベーターの設置や集会室の増築といった行為がこれに当たることになります。
◇ 共用部分の管理,変更に関する区分所有法の規定
「建物の区分所有等に関する法律」(以下,区分所有法と言います。)は,前記のようなマンション共用部分の管理,変更について,どのような規定を置いているかを確認しておきます。
の各4分の3以上の多数による集会の決議で決する。ただし,この区分所有者の定数は,規約でその過
半数まで減ずることができる。
分の所有者の承諾を得なければならない。
共有者がすることができる。
まず,管理行為のうち“保存行為”については,集会の決議は必要とせず,各共有者(区分所有者)が単独で判断して行うことができるというとになります(第18条1項但書)。この場合,区分所有法は,「各共有者は,規約に別段の定めがない限りその持分に応じて,共用部分の負担に任じ」と規定しているため(第19条),保存行為を行った共有者からの費用を求償されると,規約に別段の定めが置かれていなければ,他の共有者は応分の費用負担をしなければならないということになります。勝手に高額な費用をかけて保存行為をし,後からその負担を求めるといったことを防ぐため,規約に別段の定めが置かれていることが多いと思います。“利用行為”,“改良行為”については,第18条1項本文により,集会の決議によって決せられることになります。
次に,変更行為については,変更が共用部分の形状または効用の著しい変更になる場合と,それ以外の軽微な変更にとどまる場合とで,手続が区別されています。前者の著しい変更の場合には,4分の3以上の多数による集会の特別決議で決めなければならないのに対し(第17条1項本文。但し,この区分所有者の定数については規約で過半数まで減ずることは可能〔同項但書〕),前者の軽微な変更については,過半数による普通決議で決めることができるとされています(第18条1項の「共用部分の管理」に軽微な変更が含まれると解釈されています)。形状・効用の“著しい変更”であるか否かによって決議要件が変わってくるので,その区別が重要になるのですが,その判断は実際には簡単ではありません。マンション標準管理規約を定める国交省のコメントをみていくと,耐震工事でも基本構造部分への加工の程度が小さいものは普通決議でよいとされ,また,鉄部塗装,外壁補修,屋上防水,給排水管の更新,TV共聴設備等の工事も普通決議で足りると判断されているようです。
共用部分の変更,あるいは管理により,専有部分の使用に影響を与えることがあり得ます。区分所有法は,それが“専用部分の使用に特別の影響を及ぼすべきとき”は,その専有部分の所有者の承諾を得なければならないと規定して調整を図っています。“特別の影響”とは,「当該変更行為の必要性,有用性と当該区分所有者の受ける不利益とを比較衡量して,受忍すべき範囲を超える程度の不利益」と解されていて,その程度に至らない軽微な影響にとどまるときには承諾は不要とされています。
◇ 電力供給方式の変更と共用部分の管理
建物全体の電力量が50kw以上の中規模・大規模マンションでは,高圧電力をそのまま敷地内に置かれた受変電設備に引き込み,低圧電力に変換してから配電設備を使って各住戸に供給される仕組みとなっています。電力自由化の前に建設された中規模・大規模マンションにおいては,受変電設備,配電設備,各住戸のブレーカー,メーターといった設備はすべて電力会社が所有,管理していたのですが,2005年の電力自由化以降,中規模・大規模マンションにおいては,管理組合が電力会社から一括して高圧電力を買い取り,管理組合が所有・管理する受変電設備を使ってこれを低電圧に変圧し,各住戸に対して低圧電力を販売することが可能になりました(一括高圧受電方式)。本件の〇〇マンションも,この一括高圧受電方式の導入を目指して,本件決議等を行ったことになります。
受電方式の変更は,マンション敷地内にある受変電設備,配電設備の所有・管理形態の変更を伴いますから,これが共用部分の変更(もしくは管理)に関する事項として,総会の決議が必要となることは明らかです。しかし,本件決議や決議に基づいて作られた本件細則には,各区分所有者に対し,A社との間で結んでいる電気供給契約の解約申入れをすることを義務づける内容まで含まれるため,導入に反対する区分所有者の契約の自由,契約の相手方選択の自由との関係がさらに問題となったのです。
最高裁判所は,「裁判所の判断」のところで紹介したように,本件決議のうち,「団地建物所有権者等に個別契約の解約申入れを義務付ける部分は,専有部分の使用に関する事項を決するものであって,団地共用部分の変更又はその管理に関する事項を決するものではない」との判断を示しました。個人は誰からの干渉も受けずに自由に契約を締結することができるという「契約自由の原則」に照らすと,最高裁のこの判断は一般論としては正しいと言えます。ただ,マンションにおける個別住戸への電力の供給は,共用部分に設置された受変電設備,配電設備等を経由して行うしかないものですから,そうした電力供給の特殊性を考慮するならば,「区分所有建物にあって,電力会社から受ける電力は全体共用部分,各棟共用部分を通じて専有部分に供給されるものであるから,電力の供給元の選択においても,共同利用関係による制約を当然受けるもの」とする1審判決の判示にも説得力があったように思われます。
 コメント
コメント
1審,控訴審の判断を覆した今回の最高裁判決は,新聞報道などでも大きく取り上げられました。“マンション電力契約変更,544分の2の『抵抗』は適法”(日経),“マンションの全戸電気解約「義務づけられない」最高裁”(朝日)といった見出しからもわかるように,かなりのインパクトをもって受けとめられたようです。2016年4月からは電力小売自由化が始まり,一般の家庭でも,広く電力の売主を選択できるようになりました。マンションでも,管理組合が一括受電契約を結んでいなければ,区分所有者は電力の売主を選択することができます。そうした状況があるところに,今回,こうした最高裁の判断が示されたため,今後,マンションにおいて一括高圧受電方式に変更することは非常にハードルが高くなったと言えます。
【注目判例】 バドミントンのダブルス競技中,ペアのラケットで眼を負傷した被害者の損害賠償請求が認められた事案 : 東京高等裁判所H30.9.12判決
 事案の概要
事案の概要
X,Yの二人は,事故の1年ほど前から同じバトミントン教室に通っていた女性です(Xは40代後半)。事故があった日,XとYはペアを組み,対戦相手(A,B)とダブルスの試合をしていました。Yが相手コートから飛んできたシャトルをバックハンドで打ち返そうとラケットを振った際,そのフレームがXの左目に当たってしまい,Xは通院をして治療を受けましたが,外傷性散瞳(瞳孔が大きくなったまま,光に対する調整がきかなくなる障害)の後遺症が残ってしまいました。Xは,この事故についてYに過失があると主張し,1500万円余りの損害賠償を求めて訴訟を提起しました。
Yは,Xに損害を与えることは予見できなかったと過失を否定し,さらに,仮に過失が認められるとしても,バトミントン競技においては一定の頻度で事故が発生するのであり,競技者はそうした事故発生のリスクを引き受けて競技に参加しているから,本件のような事故の場合,ペアを組んだパートナーが負傷しても違法性が阻却されると主張しました。
1審・東京地方裁判所(平成30年2月9日判決)は,Yの過失を認定し,さらに,違法性の阻却を求めるYの主張を退ける一方,本件事故により発生した損害の全部をYに負わせるのは損害の公平な分担を図る損害賠償法の理念に反するとして,過失相殺の規定を類推適用して,YはXに生じた損害の6割を負担するのが相当であるとし,Xの請求を789万3244円の支払いを求める限度で認めました。
今回は,Yがこの1審判決を不服として控訴し,Xも附帯控訴をした事案について,東京高等裁判所が示した判断を紹介してみたいと思います。
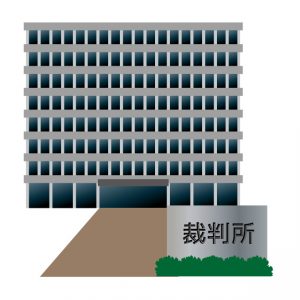
裁判所の判断
○ 本件事故についてYに過失があると言えるか
Yの過失を肯定。
相手コートの「Aが打ったシャトルは,YよりもXに近く,Xにおいて十分対応可能な位置であり,かつ,前衛であるXが打ち返すべき位置に飛来したものであ」るから,「Yは,自らが動き出す時点で,Xがシャトルを打つために動く可能性があることを予見できたというべき」である。Yは,Xの動静を把握することができなかったと主張するが,「Yは,後衛においてXとほぼ前後に並ぶ位置にいたのであるから,前衛の位置にいたXの動静を把握することができた」といえる。そのような状況の下において,Yが相手コートから飛来した「シャトルを打ちに行くのであれば,前方にいるXの動静に注意し,自身が持っているラケットがXに衝突しないよう配慮しながら競技を行う注意義務を負うものというべきであ」り,「前方にいるXの動きを把握した上で,シャトルを打ち返すことを止めるか,あるいは,少なくともラケットがXに接触しないようにラケットを相手コート側に向けて振ることにより,本件事故を回避することができた」と言えるから,Yには過失がある。
○ 本件事故につきYの行為の違法性阻却を認めるべきか
Yの違法性阻却を否定。
バトミントン協会の競技規則に「著しく反しないプレーである限り違法性が阻却されると解すると,ダブルスにおいてペアの一方によるシャトルを打ち返す際のプレーにより他方を負傷させた事故についてはどのような態様であっても違法性が否定されることになる」が,「バドミントン競技が一定の危険性を伴う競技であることを考慮しても,上記のようなルールに著しく反しない行為である以上,どのような態様によるものであってもそれにより生じた危険を競技者が全て引受けているとはいえないことは明らか」であり,違法性が阻却されると解することは相当ではない
○ Xにも過失があったとしてYの過失相殺の主張を認めるべきか
過失相殺を否定
「本件事故の発生についてXに過失はなく,損害の公平な分担の見地から,本件事故により生じたXの損害の一部を同人に負担させるべき事情が同人側に存在するとも認められないから,過失相殺ないし過失相殺類似の法理により本件事故により生じたXの損害の一部を同人に負担させる理由はない」

解 説
◇ スポーツにおける事故と損害賠償
故意,または過失によって人を傷つけてしまうと,民法の不法行為として損害賠償責任を負うことになります(709条)。スポーツをしている時に相手にケガをさせてしまった場合にも,この不法行為責任を負うことになるのでしょうか? ちょうど一年前に起きた日大アメフト部員による試合中の悪質タックル事件のように,わざと(故意に)相手チームの選手にケガを負わせた場合には,不法行為が成立することは当然ですが,ケガをさせるつもりはなかったが,接触プレーなどにより,結果としてケガを負わせてしまったケースについては,どのように考えるべきでしょうか。
ボクシングなどの格闘技,柔道・剣道などの武道については,相手とのコンタクトによる一定の危険はつきものであり,その競技に参加する者は,そのリスクがあることを承知して参加しているのであるから,ルールにしたがったプレーをしている限り,その中で他人に損害を与えたとしても(ケガを負わせたりしても),損害賠償責任を免れるという見解が以前から有力に主張されてきました。「危険の引き受けの法理」,「社会的相当性説」,「正当行為説」などが代表的な見解です。
しかし,裁判例をみてみると,ルールに従った行動が取られていたことを理由に過失を否定したものは必ずしも多くありません(ママさんバレーボール中の事故に関する事案で過失を否定したものとして東京地判S45.2.27)。むしろ,大学ラグビーの試合中,ラフプレーで被害者が重傷を負った事案について,「過失の有無は,単に競技上の規則に違反したか否かではなく,注意義務違反の有無という観点から判断すべきであり,競技規則は注意義務の内容を定めるに当たっての一つの指針となるにとどまり,規則に違反していないから過失はないとの主張は採用することができない」との判断を示した下級審判例(東京地判H26.12.3)に代表されるように,過失の成否は,当事者のそのスポーツに関する技量や経験,具体的な事故発生状況などを踏まえて,個別の事案ごとに判断されていると一般的には言えると思います。
また,違法性の阻却についても,当該スポーツのルールに従っていたというだけでこれを認めるのではなく,「当該加害行為の態様,方法が競技規則に照らして相当なものであるか,競技において通常生じうる負傷の範囲にとどまるものであるか,加害者の過失の程度などの諸要素を総合考慮して判断すべき」とされている例が多いと言えます(東京地判H28.12.26)。
◇ バトミントンをプレーする際の「過失」
それでは,本件の場合,Yには過失があったと言えるのでしょうか。
過失の成否を判断するには,その前提として,事故の発生状況の事実認定が重要になります。
本件の場合,前衛のXがショートサービスライン前後付近,センターラインからやや右寄りの位置,後衛のYがXの約3メートル後方,センターライン付近の位置にいるときに(トップ&バックの陣形),対戦相手のAが打ったシャトルが山なりにX・Yペア側のコートの左側,ショートサービスライン付近に飛んできたこと,このシャトルをYが左前方に移動して,右手のバックハンドで打ち返した時に事故が起きたことについては争いがありません。しかし,①事故直前の二人の動き(Yは,Xはラケットを構えたままシャトルを打ち返しに行く動作は一切とらなかったと主張。これに対し,Xは,シャトルを打ち返そうという体勢をとり,ラケットを振った記憶はないが,打つために足を動かして手を伸ばそうとしていたと主張),②Xがシャトルを打ちに行く際,「打つよ」と声かけをしたかどうかの2点については,X,Yの言い分に食い違いがあり,これらの点の事実認定が過失の成否に影響がありました。
判決(1審判決の事実認定を基本的には踏襲)は,①については,Xには相手コートから飛んできた「シャトルを打ち返す動作を選択することを躊躇させるような事情が認められないにもかかわらず,1年を超えるバドミントン経験を有するXが十分対応可能な位置に飛来したシャトルに対して全く反応せず,腰を落として構えるといったこともせずに立ったままで,かつ,ラケットを持つ右手を構えることもなく下に向けたまましばらく動くことがなかったということはおよそ考え難い」として,Xがシャトルを打ち返そうとする動作を一切取らなかったとするYの主張をしりぞけました(ただ,ラケットをバックハンドに構えるなどシャトルを打ち返す直前の段階には至ってはいなかったと認定)。また,②については,裁判になってからのこの点についてのYの主張・供述には変遷があり,変遷した理由についても合理的な説明がされていないとして,Yの声かけはなかったと認定しました。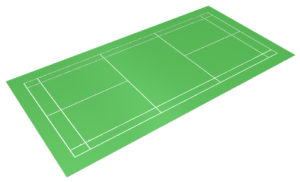
判決は,このような事実認定を前提に,Yは「前方にいるXの動きを把握した上で,シャトルを打ち返すことを止めるか,あるいは,少なくともラケットがXに接触しないようにラケットを相手コート側に向けて振ることにより,本件事故を回避することができた」としてその過失を認めました。しかし,バトミントン教室に通い始めて1年余り,技量も競技経験も乏しいYに,Xの動静をそこまで的確に予見し得たと評価してしまって構わないのか,議論のあるところだと思います。
◇ 違法性の阻却
判決は,Yの過失を認めただけでなく,Yの違法性阻却の主張も退けました。
前述の通り,違法性の阻却について過去の裁判例は,「当該加害行為の態様,方法が競技規則に照らして相当なものであるか,競技において通常生じうる負傷の範囲にとどまるものであるか,加害者の過失の程度などの諸要素を総合考慮して判断」するという判断枠組みを示していました(東京地判H28.12.26など)。
そこで,Yは,「プレーがルールに著しく違反することがなく,かつ,通常予測され許容された動作に起因するものであ」れば違法性は阻却されると主張したのですが,判決は,「バドミントン競技の場合,上記のボクシング等のように一方の競技者が他の競技者の身体に対して一定の有形力を行使することが競技の内容の一部を構成するものとは異なるから,バドミントン競技の競技者が,同競技に伴う他の競技者の故意又は過失により発生する一定の危険を当然に引き受けてこれに参加しているとまではいえない」として,Yの違法性阻却の主張を退けました。
確かに,バトミントンのようなネットを挟んで対戦相手と対峙するという競技の場合,対戦相手の身体と直接接触することによってケガをするということはほとんど考えられません。しかし,“ネット型競技”であっても,ラケットやシャトル,ボールといった道具を使うので,道具によって他のプレーヤーにケガをさせてしまうことは当然起こり得ます。一定の有形力を行使することが競技の内容の一部を構成しているかどうかという基準だけで,「危険の引き受けの法理」の適用を排除することは,必ずしも説得力があるとは言えません。
判決は,ネット型競技で起きた事故について,加害者の違法性が阻却される場面があることを一般的に否定している訳ではありませんが,コンタクトプレーがある競技と比較して,かなりその場面を限定しているように思われ,果たしてそれで妥当と言ってよいのか,やはり議論のあるところだと思います。
◇ 過失相殺について
東京高裁判決を読んで最も驚いたのは,Yの過失相殺の主張までを退け,1審判決を変更して,Xに生じた損害全ての賠償をYに命じていることです。
対戦相手がコートに打ち込んできたシャトルを打ち返すことができなければ,対戦相手に得点が入ってしまうのですから,シャトルを打ち返すためにラケットを振るということは,プレーヤーとしては本能的な行動だと言えます。また,ラケットスポーツのダブルス競技において,プレーヤーの陣形が前後になった場合,前衛としては,後衛がラケットやシャトル(ボール)を当ててこないとの信頼を有していることまでは理解できますが,シャトル(ボール)が飛んできた位置によっては,後衛のラケットや後衛が打ったシャトル,ボールなどが前衛に当たる危険は一定程度あるのですから,前衛としても,そうしたリスクを念頭において事故を回避する義務があるはずです。
1審判決は,「Yは故意をもってXを負傷させたものではなく,飛来したシャトルを打ち返すためにラケットを振るという競技の流れの中で本件事故が発生したものと評価できることに鑑みると,本件事故により発生した損害の全部を加害者であるYに負担させるのは,損害の公平な分担を図る損害賠償法の理念に反するといわざるを得ない」として過失相殺の規定の類推適用を認め,Yが負担すべき損害の範囲を6割に限定していました。6割という割合の当否は別として,やはり本事案においては,一定の過失相殺が認められて然るべきではないかと考えます。
 コメント
コメント
1審判決は,「一定の危険を伴うスポーツの競技中に事故が発生した場合に常に過失責任が問われることになれば,国民のスポーツに親しむ権利を萎縮させ,スポーツ基本法の理念にもとる結果になるから,本件については違法性が阻却されるべき」とYが主張したのに対し,「本件のように結果回避可能性が認められる場合についてまで,スポーツ競技中の事故であるからといって過失責任を否定することは,スポーツの危険性を高めることにつながりかねず,国民が安心してスポーツに親しむことを阻害する可能性がある」としてYの違法性阻却の主張を退けました。生涯スポーツの振興が国の施策として進められていますが,スポーツ事故被害者の救済を図る公的な方策はほとんど講じられていません。今回の判決のように加害者の責任を厳しく問う判断が増えるとすれば,競技を行う前に賠償責任保険に加入するなど個人でのリスクマネジメントが大切な時代になるかもしれません。
【注目判例】共同相続人間でなされた無償の相続分の譲渡は“生前贈与”にあたるとされた事例:最高裁H30.10.19判決
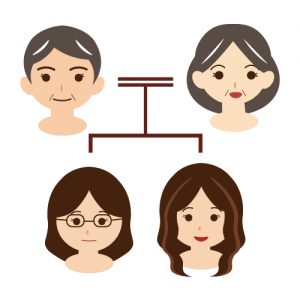 事案の概要
事案の概要
上告人Xは,被上告人Yとともに,B(父)・A(母)夫婦の子です。B・A夫婦の間には,もう一人の実子C,さらに,B・A夫婦と養子縁組をしたYの妻Dがいます。このような親族関係の下,まず,Bが平成20年12月に死亡しました。亡Bの遺産をめぐって遺産分割調停が申し立てられ,分割合意が成立する前に,Aと養子Dの二人は,それぞれ自分の相続分をYに無償で譲渡して調停手続から脱退しました(A,Dの手続からの脱退により,亡Bの遺産については,X,Y,Cの3者間において遺産分割調停手続が進められ,平成22年12月に遺産分割調停が成立しました)。その後,Aは,平成22年8月,全財産をYに相続させる旨の公正証書遺言を作成しました。
亡Bの遺産相続をめぐって以上のような経緯があった後,平成26年7月,今度はAが亡くなりました。死亡時,Aには介護費用の債務とほぼ同額のわずかな預金しかありませんでした。しかし,Aは,前述の通り,生前,Bの相続分を無償でYに譲渡しています。この相続分の無償譲渡は民法903条1項が規定する贈与にあたり,これによって自己の遺留分が侵害されているとして,XがYに対して遺留分減殺請求を行ったというのが本件事案になります。
原審・東京高等裁判所(平成29年6月22日判決)は,ア)相続分の譲渡による相続財産の持分の移転は,遺産分割が終了するまでの暫定的なものであり,最終的に遺産分割が確定すれば,その遡及効によって,相続分の譲受人は相続開始時に遡って被相続人から直接財産を取得したことになるから,譲渡人から譲受人に相続財産の贈与があったとは観念できない,イ)相続分の譲渡は必ずしも譲受人に経済的利益をもたらすものとはいえず,譲渡に係る相続分に経済的利益があるか否かは当該相続分の積極財産及び消極財産の価額等を考慮して算定しなければ判明しないなどとして,本件相続分譲渡は,その価額を遺留分算定の基礎となる財産額に算入すべき贈与(民法1044条,903条1項)には当たらないと判断し,Xの請求を斥けました。
今回は,Xの上告受理申し立てに対して最高裁が示した判断を紹介したいと思います。
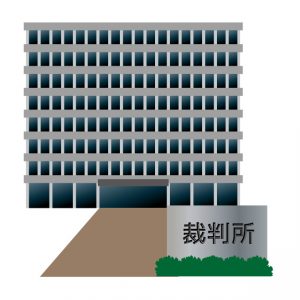 裁判所の判断
裁判所の判断
〇 共同相続人間においてされた無償の相続分譲渡は民法903条1項に規定する「贈与」にあたるか
「相続分の譲渡は、譲渡に係る相続分に含まれる積極財産及び消極財産の価額等を考慮して算定した当該相続分に財産的価値があるとはいえない場合を除き、譲渡人から譲受人に対し経済的利益を合意によって移転するものということができ」,「遺産の分割が相続開始の時に遡ってその効力を生ずる(民法909条本文)とされていることは,以上のように解することの妨げとなるものではない」から,共同相続人間においてされた無償による相続分の譲渡は,譲渡に係る相続分に含まれる積極財産及び消極財産の価額等を考慮して算定した当該相続分に財産的価値があるとはいえない場合を除き,上記譲渡をした者の相続において,民法903条1項に規定する「贈与」に当たる。
 解説
解説
◇ 遺留分について
「遺留分」とは,兄弟姉妹以外の法定相続人について法律で保障されている最低限度の相続分といいます。被相続人が法定相続人にとって非常に不公平,不平等な遺言や生前贈与をした場合,この遺留分の限度で,遺産の一部を取り戻すことができるという仕組みです。遺留分が保障されている法定相続人(遺留分権利者と言います。)は,①配偶者,②子ども,③父母・祖父母など直系尊属です。②の子どもには,実子だけでなく養子も含まれますし,子がすでに亡くなっている場合の代襲相続人にも遺留分が認められます。他方で,被相続人の兄弟姉妹は,第3順位の法定相続人ですが,法律上,遺留分は認められていません(民法1028条)。相続財産に対する遺留分全体の割合は,原則として2分の1です。直系尊属(父母,祖父母)だけが相続人となるというパターンのときだけ,例外として3分の1が遺留分となります。遺留分権利者が複数いる場合には,この遺留分割合を各相続人の法定相続分で配分します。
本件の事案は,子どものみが相続人となるケースとなるので,相続財産に対する遺留分全体の割合は2分の1となります。そして,Aの子は,X,Y,C,Dの4名いますから,各自の遺留分は1/8(1/4×1/2)ということになります。
◇ 遺留分の基礎となる財産
遺留分を計算するには,まず,遺留分の基礎となる財産を確定させる作業が必要になります。
遺留分は,「被相続人が相続開始の時において有した財産の価額にその贈与した財産の価額を加えた額から債務の全額を控除して,これを算定する」とされています(民法1029条)。つまり,ア)相続開始時に現存している財産に,イ)生前に贈与した財産を加え,そこから,ウ)債務を差し引いたものが,遺留分を計算する際の基礎となる財産ということになります。
イ)の「生前に贈与した財産」にどこまでの範囲のものが含まれるかについては,相続人以外の第三者に贈与した財産と,相続人に生前贈与した財産とに分けてみておく必要があります。相続人以外の第三者に贈与した財産については,原則として,相続開始前1年以内に贈与されたものに限って遺留分算定の基礎となる財産に算入するということになっています。但し,1年以上前に贈与したものであっても,贈与当事者の双方が遺留分権利者に損害を加える結果となることを知って贈与したものは,基礎となる財産に算入することになります(民法1030条)。これに対し,相続人に生前贈与した財産については,それが民法903条1項が規定する『特別受益』に該当する贈与といえる場合には,1年以上前の贈与であったとしても,遺留分を計算する際の基礎となる財産に含めることとされています(最高裁平成10年3月24日判決)。なお,特別受益にあたらない贈与については,民法1030条に従って処理されることになります。
◇ 特別受益とは?
特別受益に該当する贈与とはどのようなものでしょうか。この点について民法は,「共同相続人中に,被相続人から,遺贈を受け,又は婚姻若しくは養子縁組のため若しくは生計の資本として贈与を受けた者があるとき」を特別受益としています(903条1項)。「遺贈」とは遺言によって遺産を無償で他人に譲渡することです。特定の相続人に遺贈を行うとすべて特別受益になります。「婚姻若しくは養子縁組のために受けた贈与」は,“持参金”,“支度金”といったものがこれに該当します。「生計の資本として受けた贈与」としては,例えば,子どもが独立をした時に贈与した不動産,あるいは不動産の購入費用などが典型的なものとなります。子どもの学費については,高校の学費までは親の子に対する扶養義務履行の範囲内とされ,特別受益にはあたりません。 特別受益にあたる贈与があるケースでは,贈与による利益を受けた相続人(受益者)から相続分を減額することになります。減額の方法として,特別受益の持ち戻し計算というものを行います。これは,死亡時に残された遺産に受益者が受けた贈与分を加えて“みなし相続財産”というものを想定し,ここから法定相続分に従って遺産配分をするという計算方法になります。こうした特別受益の制度は,生前贈与や遺贈をした被相続人の意思を尊重しつつも,生前贈与や遺贈の「持ち戻し」をすることにより,法定相続分に修正を加えて相続人間の実質的な公平を保とうとする仕組みになります。
◇ 相続分の無償譲渡は民法903条1項の特別受益に該当する贈与にあたるのか
特別受益の仕組みを規定している民法903条1項の条文は,先ほど見ていただいたように「贈与を受けた者」となっているので,相続分を無償で譲り受けた者をこれと同じに扱うべきかについては争いがあり,下級審の裁判例も結論が分かれていました。本件の原審(東京高等裁判所・平成29年6月22日判決)は,冒頭で述べたようにこれを消極的に解した訳ですが,同じ東京高等裁判所の別の判決では,相続分の無償の譲渡によって「財産的価値の増加があるのであるから,相続分の譲渡についても特別受益としての生計の資本の贈与に該当し得る」と本件原審とは異なる判断が示されていました(東京高裁・平成29年7月6日判決:判例時報2370号31頁)。最高裁がどちらの解釈を支持するか注目されていた訳ですが,相続分の無償譲渡は原則として民法903条1項の特別受益にあたる,ただ,譲渡に係る相続分に含まれる積極財産及び消極財産の価額等を考慮して算定した当該相続分に財産的価値があるとはいえない場合は例外的に特別受益にはあたらない,という判断基準が示されたのです。
 コメント
コメント
今回の最高裁判決により,相続分の無償譲渡は原則として特別受益に該当するということになったので,相続分の譲渡を検討する際には,相続人となることが予定される者の遺留分を侵害することがないかを考慮する必要があります。また,今回の事例は共同相続人の間で相続分の譲渡が行われたというものでしたが,遺産分割協議や遺産分割調停によってBの遺産に関するAの法定相続分をYに取得させるという合意が成立することもあります。その場合,やはり特別受益の問題が生じることになるのかは残された課題となります。
【注目判例】正社員と非正規社員の賃金・手当等の格差がどこまで許容されるかを示した2つの最判:最高裁H30.6.1 ハマキョウレックス,長澤運輸両事件
正社員と非正規正社員との間で賃金や手当などについて差を設けることは許されるのでしょうか。また,許される場合があるとして,労働条件のどの部分について,どの程度まで差をつけることができるのでしょうか。
これまで正社員と非正規社員との間では,労働条件・待遇に差をつけることが当たり前という風潮があったように思います。しかし,2013(平成25)年4月に施行された改正労働契約法には,契約期間が“無期”であるか“有期”であるかによって労働条件に不合理な差をつけてはならないという規定が新たに設けられました(労働契約法第20条)。法改正後,この労契法20条の規定を使って,正社員との間の労働条件・待遇の格差の是正を求める裁判が全国各地で起こされるようになりました。
このような中,今年6月1日,最高裁判所は,ハマキョウレックス事件と長澤運輸事件という2つの事件について,正社員と非正規社員との待遇格差がこの労働契約法第20条の規定によりどのような場合に不合理なものとして無効となるのかについて,非常に注目される判断を示しました。今回は,この2つの事件についての最高裁の判断をご紹介します。
その1)ハマキョウレックス事件 -正社員と契約社員との間の待遇格差が問題とされたケース-
事案の概要
 ハマキョウレックス事件は,大手物流会社における契約社員と正社員との間の労働条件・待遇の格差が問題となった事案です。H支店で勤務する契約社員X(貨物自動車の運転手)が,会社(Y)に対して,労働契約法第20条に基づいて,①正社員と契約社員との間の『賃金』の差額の支払い,②正社員にのみ支給されている『諸手当』の支払い(無事故手当,業務手当,給食手当,住宅手当,皆勤手当,通勤手当),③正社員にのみ認められる“賞与”,“退職金”の支給を求めたという事案です。平成28年9月16日に言い渡しのあった大津地裁彦根支部の一審判決は,正社員は将来支店長等として被告会社の中核を担う可能性があること等の責任を有するが,契約社員は事業の中核を担う人材として育成されるべき立場にはないとして,賃金差額(①)や賞与・退職金の支給(③)のみならず,通勤手当以外の諸手当についてもこれを契約社員について支給しないとしても不合理な相違とは言えないとして,Xの労働契約法20条違反の主張を基本的にはしりぞけました。これに対し,平成28年9月16日に大阪高等裁判所が下した控訴審判決では,基本的な判断枠組みについては大津地裁彦根支部の一審判決を維持しつつ,通勤手当以外の無事故手当,作業手当,給食手当についても契約社員に対して不支給とすることは不合理な相違として労働契約法20条に違反するとし,一審と比べるとXに有利な判断を示していました。
ハマキョウレックス事件は,大手物流会社における契約社員と正社員との間の労働条件・待遇の格差が問題となった事案です。H支店で勤務する契約社員X(貨物自動車の運転手)が,会社(Y)に対して,労働契約法第20条に基づいて,①正社員と契約社員との間の『賃金』の差額の支払い,②正社員にのみ支給されている『諸手当』の支払い(無事故手当,業務手当,給食手当,住宅手当,皆勤手当,通勤手当),③正社員にのみ認められる“賞与”,“退職金”の支給を求めたという事案です。平成28年9月16日に言い渡しのあった大津地裁彦根支部の一審判決は,正社員は将来支店長等として被告会社の中核を担う可能性があること等の責任を有するが,契約社員は事業の中核を担う人材として育成されるべき立場にはないとして,賃金差額(①)や賞与・退職金の支給(③)のみならず,通勤手当以外の諸手当についてもこれを契約社員について支給しないとしても不合理な相違とは言えないとして,Xの労働契約法20条違反の主張を基本的にはしりぞけました。これに対し,平成28年9月16日に大阪高等裁判所が下した控訴審判決では,基本的な判断枠組みについては大津地裁彦根支部の一審判決を維持しつつ,通勤手当以外の無事故手当,作業手当,給食手当についても契約社員に対して不支給とすることは不合理な相違として労働契約法20条に違反するとし,一審と比べるとXに有利な判断を示していました。
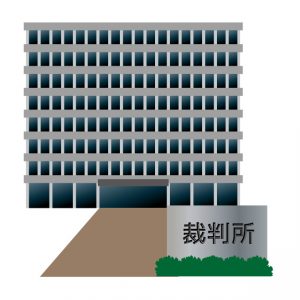 最高裁判所の判断
最高裁判所の判断
〇 労働契約法20条の規定の意味内容
労働契約法20条は,「有期契約労働者と無期契約労働者との間で労働条件に相違があり得ることを前提に,職務の内容,当該職務の内容及び配置の変更の範囲その他の事情を考慮して,その相違が不合理と認められるものであってはならないとするものであり,職務の内容等の違いに応じた均衡のとれた処遇を求める規定であると解され」る。
〇 労働契約法20条の違反があった場合の有期契約労働者の労働条件
同条の規定は「私法上の効力を有するものと解するのが相当であり,有期労働契約のうち同条に違反する労働条件の相違を設ける部分は無効となるものと解される」が,条文の文言上,「両者の労働条件の相違が同条に違反する場合に,当該有期契約労働者の労働条件が比較の対象である無期契約労働者の労働条件と同一のものとなる旨を定めていない」ことから,「有期契約労働者と無期契約労働者との労働条件の相違が同条に違反する場合であっても,同条の効力により当該有期契約労働者の労働条件が比較の対象である無期契約労働者の労働条件と同一のものとなるものではない」と解するのが相当であり,また,Y社においては,正社員に適用される就業規則・給与規程と,契約社員に適用される就業規則とが別個独立のものとして作成されていること等にも鑑みると,「両者の労働条件の相違が同条に違反する場合に,本件正社員就業規則又は本件正社員給与規程の定めが契約社員であるXに適用されることとなると解することは,就業規則の合理的な解釈としても困難」であるから,仮に本件賃金等に係る相違が労働契約法20条に違反するとしても,Xが,賃金等について正社員と同一の権利を有する地位にあることの確認を求める本件確認請求には理由がなく,また,同一の権利を有する地位にあることを前提とする本件差額賃金請求も理由がない。
〇 労働契約法20条の「不合理と認められるもの」の解釈
Xらは,労働契約法第20条の「不合理と認められるもの」とは“合理的でないもの”と同義であると解すべきと主張するが,「同条が『不合理と認められるものであってはならない』と規定していることに照らせば,同条は飽くまでも労働条件の相違が不合理と評価されるか否かを問題とするものと解することが文理に沿うものといえ」,また,「同条は,職務の内容等が異なる場合であっても,その違いを考慮して両者の労働条件が均衡のとれたものであることを求める規定であるところ,両者の労働条件が均衡のとれたものであるか否かの判断に当たっては,労使間の交渉や使用者の経営判断を尊重すべき面があることも否定し難い」から,同条にいう「不合理と認められるもの」とは,有期契約労働者と無期契約労働者との労働条件の相違が不合理であると評価することができるものであることをいうと解するのが相当である。
〇 大阪高裁が不合理とは認めなかった「住宅手当」「皆勤手当」の格差が労働契約法20条に違反するか
本件の事実関係の下では,正社員のトラック運転手と契約社員のトラック運転手との間には,「両者の職務の内容に違いはないが,職務の内容及び配置の変更の範囲に関しては,正社員は,出向を含む全国規模の広域異動の可能性があるほか,等級役職制度が設けられており,職務遂行能力に見合う等級役職への格付けを通じて,将来,Y社の中核を担う人材として登用される可能性があるのに対し,契約社員は,就業場所の変更や出向は予定されておらず,将来,そのような人材として登用されることも予定されていないという違いがあ」り,そうすると,「住宅手当は,従業員の住宅に要する費用を補助する趣旨で支給されるものと解されるところ,契約社員については就業場所の変更が予定されていないのに対し,正社員については,転居を伴う配転が予定されているため,契約社員と比較して住宅に要する費用が多額となり得る」から,「正社員に対して上記の住宅手当を支給する一方で,契約社員に対してこれを支給しないという労働条件の相違は,不合理であると評価することができるものとはいえない」ので,労働契約法20条に違反するとは言えない。これに対し,皆勤手当については,「Y社が運送業務を円滑に進めるには実際に出勤するトラック運転手を一定数確保する必要があることから,皆勤を奨励する趣旨で支給されるものであると解されるところ,Y社の乗務員については,契約社員と正社員の職務の内容は異ならないから,出勤する者を確保することの必要性については,職務の内容によって両者の間に差異が生ずるものではな」く,また,実際に出勤する運転手を一定数確保するとの必要性は,「当該労働者が将来転勤や出向をする可能性や,Y社の中核を担う人材として登用される可能性の有無といった事情により異なるとはいえ」ず,さらに,Y社においては労働契約や就業規則で契約社員についても「会社の業績と本人の勤務成績を考慮して昇給することがあるとされているが,昇給しないことが原則である上,皆勤の事実を考慮して昇給が行われたとの事情もうかがわれない」から,「Y社の乗務員のうち正社員に対して上記の皆勤手当を支給する一方で,契約社員に対してこれを支給しないという労働条件の相違は,不合理であると評価することができ」,労働契約法20条に違反すると解するのが相当である。
〇 大阪高裁が不合理な相違とした「無事故手当」「作業手当」「給食手当」「通勤手当」の格差が労働契約法20条に違反するか
「無事故手当は,優良ドライバーの育成や安全な輸送による顧客の信頼の獲得を目的として支給されるものであると解されるところ,Y社の乗務員については,契約社員と正社員の職務の内容は異ならないから,安全運転及び事故防止の必要性については,職務の内容によって両者の間に差異が生ずるものではな」く,また,安全運転及び事故防止の必要性は,「当該労働者が将来転勤や出向をする可能性や,Y社の中核を担う人材として登用される可能性の有無といった事情により異なるものではな」いから,「Y社の乗務員のうち正社員に対して無事故手当を支給する一方で,契約社員に対してこれを支給しないという労働条件の相違は,不合理であると評価することができ」,労働契約法20条に違反する。
「作業手当は,特定の作業を行った対価として支給されるものであり,作業そのものを金銭的に評価して支給される性質の賃金であると解される」ところ,「Y社の乗務員については,契約社員と正社員の職務の内容は異なら」ず,「また,職務の内容及び配置の変更の範囲が異なることによって,行った作業に対する金銭的評価が異なることになるものではな」いから,「Y社の乗務員のうち正社員に対して上記の作業手当を一律に支給する一方で,契約社員に対してこれを支給しないという労働条件の相違は,不合理であると評価することができ」,労働契約法20条に違反する。
「給食手当は,従業員の食事に係る補助として支給されるものであるから,勤務時間中に食事を取ることを要する労働者に対して支給することがその 趣旨にかなうものである。しかるに,Y社の乗務員については,契約社員と正社員の職務の内容は異ならない上,勤務形態に違いがあるなどといった事情はうかがわれ」ず,また,「職務の内容及び配置の変更の範囲が異なることは,勤務時間中に食事を取ることの必要性やその程度とは関係がない」から,「Y社の乗務員のうち正社員に対して上記の給食手当を支給する一方で,契約社員に対してこれを支給しないという労働条件の相違は,不合理であると評価することができ」,労働契約法20条に違反する。
「通勤手当は,通勤に要する交通費を補塡する趣旨で支給されるものであるところ,労働契約に期間の定めがあるか否かによって通勤に要する費用が異なるものではな」く,また,「職務の内容及び配置の変更の範囲が異なることは,通勤に要する費用の多寡とは直接関連するものではない」から,「正社員と契約社員であるXとの間で上記の通勤手当の金額が異なるという労働条件の相違は,不合理であると評価することができ」,労働契約法20条に違反する。
その2)長澤運輸事件 -正社員と定年後再雇用職員との間の待遇格差が問題とされたケース
事案の概要
 長澤運輸事件は,従業員数約100名の貨物運送会社(Y)において,定年退職後に嘱託乗務員(有期雇用)として再雇用された運転手(3名。Xら)が,定年前と全く同じ業務に従事しているにもかかわらず賃金総額で2割強減額されたことは労働契約法第20条に違反しているとして,主位的に嘱託乗務員についても正社員の就業規則・賃金規程等が適用されるべきであるとして賃金差額の支払いを,予備的に賃金差額に相当する損害賠償の請求を求めたという事案です。ハマキョウレックス事件と同様,物流会社のトラック運転手として働く非正規職員の事案ですが,60歳で定年年齢を迎え,その後,再雇用された従業員の事案という点で違いがあります。
長澤運輸事件は,従業員数約100名の貨物運送会社(Y)において,定年退職後に嘱託乗務員(有期雇用)として再雇用された運転手(3名。Xら)が,定年前と全く同じ業務に従事しているにもかかわらず賃金総額で2割強減額されたことは労働契約法第20条に違反しているとして,主位的に嘱託乗務員についても正社員の就業規則・賃金規程等が適用されるべきであるとして賃金差額の支払いを,予備的に賃金差額に相当する損害賠償の請求を求めたという事案です。ハマキョウレックス事件と同様,物流会社のトラック運転手として働く非正規職員の事案ですが,60歳で定年年齢を迎え,その後,再雇用された従業員の事案という点で違いがあります。
1審の東京地裁は,平成28年5月13日,Xらの請求をほぼ全面的に認める判決を下しましたが,2審の東京高裁は,定年後再雇用時の賃金引き下げは社会で一般的に行われており,「2割程度の賃金減額は社会的に許容される」として,逆にXらの請求を全面的にしりぞけました。この判決を不服としてXらが上告したのが本事案です。
最高裁判所の判断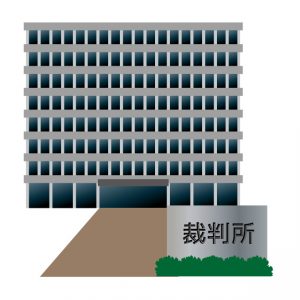
〇 労契法第20条に示された不合理性の判断要素のうち「その他の事情」の扱い -“職務内容及び変更範囲に関連する事情”に限られるか?-
「Y社における嘱託乗務員及び正社員は,その業務の内容及び当該業務に伴う責任の程度に違いはなく,業務の都合により配置転換等を命じられることがある点でも違いはないから,両者は,職務の内容並びに当該職務の内容及び配置の変更の範囲において相違はないということができる」が,「労働者の賃金に関する労働条件は,労働者の職務内容及び変更範囲により一義的に定まるものではなく,使用者は,雇用及び人事に関する経営判断の観点から,労働者の職務内容及び変更範囲にとどまらない様々な事情を考慮して,労働者の賃金に関する労働条件を検討するもの」であり,また,「労働者の賃金に関する労働条件の在り方については,基本的には,団体交渉等による労使自治に委ねられるべき部分が大きい」と言うこともできる。そうすると,「労働契約法20条は,有期契約労働者と無期契約労働者との労働条件の相違が不合理と認められるものであるか否かを判断する際に考慮する事情として,『その他の事情』を挙げているところ,その内容を職務内容及び変更範囲に関連する事情に限定すべき理由は見当たら」ない。
〇 Xが定年退職後に再雇用された者であることを「その他の事情」として考慮することができるか
「Y社における嘱託乗務員は,Y社を定年退職した後に,有期労働契約により再雇用された者である。定年制は,使用者が,その雇用する労働者の長期雇用や年功的処遇を前提としな
がら,人事の刷新等により組織運営の適正化を図るとともに,賃金コストを一定限度に抑制するための制度ということができるところ,定年制の下における無期契約労働者の賃金体系は,当該労働者を定年退職するまで長期間雇用することを前提に定められたものであることが少なくないと解される。これに対し,使用者が定年退職者を有期労働契約により再雇用する場合,当該者を長期間雇用することは通常予定されていない。また,定年退職後に再雇用される有期契約労働者は,定年退職するまでの間,無期契約労働者として賃金の支給を受けてきた者であり,一定の要件を満たせば老齢厚生年金の支給を受けることも予定されている。そして,このような事情は,定年退職後に再雇用される有期契約労働者の賃金体系の在り方を検討するに当たって,その基礎になるものであるということができる」から,有期契約労働者が定年退職後に再雇用された者であることは,労働契約法20条にいう『その他の事情』として考慮されることとなる事情に当たると解するのが相当である。
〇 嘱託乗務員と正社員との賃金格差の比較方法
「Y社における嘱託乗務員と正社員との本件各賃金項目に係る労働条件の相違が問題となるところ,労働者の賃金が複数の賃金項目から構成されている場合,個々の賃金項目に係る賃金は,通常,賃金項目ごとに,その趣旨を異にするものであるということができ」るから,「有期契約労働者と無期契約労働者との賃金項目に係る労働条件の相違が不合理と認められるものであるか否かを判断するに当たっては,当該賃金項目の趣旨により,その考慮すべき事情や考慮の仕方も異なり得るというべき」であり,「そうすると,有期契約労働者と無期契約労働者との個々の賃金項目に係る労働条件の相違が不合理と認められるものであるか否かを判断するに当たっては,両者の賃金の総額を比較することのみによるのではなく,当該賃金項目の趣旨を個別に考慮すべきものと解するのが相当」である。
〇 嘱託乗務員と正社員との各賃金項目における格差が不合理なものと認められるか
* 嘱託乗務員について能率給・職務給を支給していない点
「嘱託乗務員は定年退職後に再雇用された者であり,一定の要件を満たせば老齢厚生年金の支給を受けることができる上,Y社は,本件組合との団体交渉を経て,老齢厚生年金の報酬比例部分の支給が開始されるまでの間,嘱託乗務員に対して2万円の調整給を支給することとしている」などの事情を総合考慮すると,「正社員に対して能率給及び職務給を支給する一方で,嘱託乗務員に対して能率給及び職務給を支給せずに歩合給を支給するという労働条件の相違は,不合理であると評価することができるものとはいえ」ず,労働契約法第20条に違反するものとは言えない。
* 嘱託乗務員に精勤手当を支給していない点
「Y社における精勤手当は,その支給要件及び内容に照らせば,従業員に対して休日以外は1日も欠かさずに出勤することを奨励する趣旨で支給されるものであるということができる」が,「Y社の嘱託乗務員と正社員との職務の内容が同一である以上,両者の間で,その皆勤を奨励する必要性に相違はない」というべきである。「嘱託乗務員の歩合給に係る係数が正社員の能率給に係る係数よりも有利に設定されていることには,Y社が嘱託乗務員に対して労務の成果である稼働額を増やすことを奨励する趣旨が含まれているとみることもできるが,精勤手当は,従業員の皆勤という事実に基づいて支給されるものであるから,歩合給及び能率給に係る係数が異なることをもって,嘱託乗務員に精勤手当を支給しないことが不合理でないということはできない」から,正社員に対して精勤手当を支給する一方で,嘱託乗務員に対してこれを支給しないという労働条件の相違は,労働契約法第20条に違反する。
* 嘱託乗務員に住宅手当・家族手当を支給していない点
「Y社における住宅手当及び家族手当は,その支給要件及び内容に照らせば,前者は従業員の住宅費の負担に対する補助として,後者は従業員の家族を扶養するための生活費に対する補助として,それぞれ支給されるもの」ということができ,「いずれも労働者の提供する労務を金銭的に評価して支給されるものではなく,従業員に対する福利厚生及び生活保障の趣旨で支給されるもの」であるから,使用者がそのような賃金項目の要否や内容を検討するに当たっては,各手当を支給する趣旨に照らして,労働者の生活に関する諸事情を考慮することになるものと解される。「Y社における正社員には,嘱託乗務員と異なり,幅広い世代の労働者が存在し得るところ,そのような正社員について住宅費及び家族を扶養するための生活費を補助することには相応の理由がある」ということができ,他方,「嘱託乗務員は,正社員として勤続した後に定年退職した者であり,老齢厚生年金の支給を受けることが予定され,その報酬比例部分の支給が開始されるまでは被上告人から調整給を支給されることとなっている」などの事情を総合考慮すると,「正社員に対して住宅手当及び家族手当を支給する一方で,嘱託乗務員に対してこれらを支給しないという労働条件の相違は,不合理であると評価することができるものとはいえ」ず,労働契約法第20条に違反するものとは言えない。
* 嘱託乗務員に役付手当を支給していない点
「Xらは,嘱託乗務員に対して役付手当が支給されないことが不合理である理由として,役付手当が年功給,勤続給的性格のものである旨主張しているところ,Y社における役付手当は,その支給要件及び内容に照らせば,正社員の中から指定された役付者であることに対して支給されるものであるということができ,Xらの主張するような性格のものということはできない」から,「正社員に対して役付手当を支給する一方で,嘱託乗務員に対してこれを支給しないという労働条件の相違は,労働契約法20条にいう不合理と認められるものに当たると」は言えない。
* 嘱託乗務員の時間外手当の算定基礎に精勤手当が含まれない点
「Y社は,正社員と嘱託乗務員の賃金体系を区別して定めているところ,割増賃金の算定に当たり,割増率その他の計算方法を両者で区別していることはうかがわれない」が,前述の通り「嘱託乗務員に精勤手当を支給しないことは,不合理であると評価することができるものに当たり,正社員の超勤手当の計算の基礎に精勤手当が含まれるにもかかわらず,嘱託乗務員の時間外手当の計算の基礎には精勤手当が含まれないという労働条件の相違は,不合理であると評価」することができ,労働契約法第20条に違反する。
* 嘱託乗務員に賞与が支給されない点
「賞与は,月例賃金とは別に支給される一時金であり,労務の対価の後払い,功労報償,生活費の補助,労働者の意欲向上等といった多様な趣旨を含み得るもの」であるところ,「嘱託乗務員は,定年退職後に再雇用された者であり,定年退職に当たり退職金の支給を受けるほか,老齢厚生年金の支給を受けることが予定され,その報酬比例部分の支給が開始されるまでの間は被上告人から調整給の支給を受けることも予定されてい」ているし,「また,本件再雇用者採用条件によれば,嘱託乗務員の賃金(年収)は定年退職前の79%程度となることが想定され」ているなど,Y社の嘱託乗務員の賃金体系は,「嘱託乗務員の収入の安定に配慮しながら,労務の成果が賃金に反映されやすくなるように工夫した内容になっている」ことなどに照らすと,「嘱託乗務員と正社員との職務内容及び変更範囲が同一であり,正社員に対する賞与が基本給の5か月分とされているとの事情を踏まえても,正社員に対して賞与を支給する一方で,嘱託乗務員に対してこれを支給しないという労働条件の相違は,不合理であると評価することができるものとはいえ」ず,労働契約法第20条に違反するとは言えない。
 解説
解説
1,2つの最高裁判決の位置づけ
最高裁判所は,同じ日にこの2つの判決を下しています。ただ,ハマキョウレックス事件は,正社員と非正規社員(契約社員)との間の労働条件の格差が問題とされた事案であるのに対し,長澤運輸事件は,有期労働者の中でも定年後再雇用された嘱託乗務員と正社員との労働条件の格差が問題とされた事案であることから,前者の判決の方が,より一般的なケースについての広い射程距離を持った判断であると言えると思います(実際,最高裁は,先にハマキョウレックス事件の判決の言い渡しを行っていて,その2時間後に言い渡された長澤運輸事件の判決では,ハマキョウレックスの判示部分を数多く引用しています)。労契法第20条の適用が想定される典型的な事案について,最高裁としての基本的な判断枠組み,解釈基準を明らかにしたのがハマキョウレックス事件の最高裁判決であり,正社員(無期契約労働者)と契約社員など有期契約労働者との労働条件の格差(判決では“相違”という表現が使われています。)をどのように処理すべきかについて,非常に重要な判断基準を提供していると言えます。
2,労働契約法第20条の基本的意義
労働契約法第20条は,「期間の定めがあることによる」不合理な労働条件の相違を設けることを禁止した規定です。他方で,期間の定めがあることにより労働条件に差をつけることがすべて禁じられているのかというとそうではなく,「労働者の業務の内容及び当該業務に伴う責任の程度,当該職務の内容及び配置の変更の範囲その他の事情を考慮して、不合理と認められるものであってはならない」と条文にあることから,『職務内容』,『配置の変更の範囲』(=人材活用の仕組み),『その他の事情』を理由とする一定の相違があっても不合理ではないとされる場合があることになります。この点について,正社員と有期社員との間で「職務内容」および「人材活用の仕組み」が同一である場合には,労契法第20条により同一の待遇が要求されることになるとの説(均等待遇説)も有力に唱えられていたのですが,最高裁は,「職務の内容等の違いに応じた均衡のとれた処遇を求める規定」であると判断しました(均衡待遇説)。
3,労働契約法20条の違反があった場合の有期契約労働者の労働条件
労契法第20条が職務内容等の違いに応じた均衡のとれた処遇を求める規定として理解すると(均衡待遇説),労働条件の違いに不合理性が認められた場合であっても,労契法第20条の規定を根拠にストレートに正社員(無期契約労働者)と同一の労働条件の適用を求めることはできません。賃金格差の是正を求めるようなケースでは,就業規則等に特別な補充規範が存在するような場合でない限り,労契法第20条の違反は損害賠償請求という形で処理されることになります。
4,「不合理と認められるもの」,「その他の事情」の解釈
今回の最高裁判決で一般の人にわかりにくいのは,この労契法第20条の「不合理と認められるもの」の解釈を示している部分ではないかと思います。最高裁は,労契法第20条が禁止しているのは,労働条件に不合理な格差を設けてはいけないということであって,格差が合理的であることを求めているわけではない,という趣旨の論理を展開しています。しかし,不合理であってはならない=合理的でなければならない,と考えるのが一般的な国語の解釈ではないかと思います。しかも,「不合理と認められる」か否かの判断に際しては,労使間の交渉の経緯や使用者の経営判断なども尊重すべきという趣旨の一文も入っているため,いかなる場合に労働条件の相違が不合理と判断されることになるのか,非常に予測しにくい判断枠組みになってしまっていると言えます。
5,「その他の事情」として斟酌し得るもの
4にも関連することですが,長澤運輸事件においては,「その他の事情」としてXが定年後再雇用された者であるこという事情を考慮できるかが争点となり,最高裁は,「その他の事情」には「職務の内容」「職務の内容及び配置の変更の範囲」と特に関連を持たないものまで判断要素として取り込むことができ,Xが定年後再雇用された者であることも,まさに「その他の事情」として判断要素となることを明らかにしました。この結果,労契法第20条の適用が争われている事案のうち,定年後再雇用された有期労働者の事案においては,企業側が高年法の改正に伴い定年後再雇用に対応することになった経緯や実際の対応経過などがある程度尊重されることになりそうです。
6,具体的な賃金項目についての判断
最高裁は,ハマキョウレックス事件においては,一時金(賞与),退職金,住宅手当を除いた5つの手当について,これを契約社員に支給しないこととしていることについて不合理性を認めました。各手当の性格,支給目的と正社員・契約社員の職務の内容等との対比において,格差を設けることが不合理と認められるとしている部分については,説得力がありますし,他の事案においても非常に参考になると思います。住宅手当を契約社員についてだけ支給していない点について,契約社員には転居を伴う配転が予定されていないことを根拠に不合理とは言えないとする判断も,職務内容・人材活用の仕組みにかかわる違いがあることの結果と捉えれば,やむを得ないところかもしれません。
最高裁は,長澤運輸事件においては,正社員と定年後再雇用の嘱託乗務員との間の格差のうち,精勤手当を支給しないこととしている部分についてだけ不合理性を認めました。ただ,注意しなければならないのは,この長澤運輸の事案では,労使交渉の結果,Y社からXらに対して老齢年金受給開始年齢までは調整額が支給されることになっており,また,支給される賃金総額も定年退職前の約80%の水準となっていることが,不合理性を否定する判断につながっているということです。つまり,長澤運輸事件の最高裁判決から,“定年後再雇用の場合には,労働条件に差をつけることが許される”という一般的な基準を読み取ることはできないのであって,不合理性が認められるか否かはあくまで個別の事案によって異なってくるということです。
