注目判例&新法情報
一覧
【注目判例】定年後再雇用の賃金を合理的な理由なく退職前と比べて約75%減額する提示をしたことは違法とされた事例:福岡高裁H29.9.7判決
 事案の概要
事案の概要
Xは,北九州市にある食品会社(Y社)で昭和48年から正社員として勤務していましたが,平成27年3月に満60歳となり,同月末日に定年となりました。Xは,定年後もフルタイムの勤務を希望していましたが,Y社から示された再雇用契約の条件は,勤務日は週3日,1日の勤務時間は実働6時間,賃金は時間給で900円というものでした(本件提案。※ 提示された条件の細かな部分はここでは省略します)。
Xは,Y社から示された本件提案を承諾せず,定年後も定年前賃金の8割相当額を賃金とする合意が黙示的に成立していると主張して,定年退職日以降もY社の従業員としての地位があることの確認と定年前賃金の8割相当額の支払いを求め,さらに,予備的に,Y社が再雇用契約へ向けた条件提示を行うに際し,賃金が著しく低廉で不合理な労働条件の提示しか行わなかったことはXの再雇用の機会を侵害する不法行為を構成するとして,慰謝料等の支払いを求めました。
1審の福岡地方裁判所小倉支部は,Xは平成27年3月31日をもってY社を定年退職して再雇用に至らなかったに過ぎないとして,従業員としての地位の確認と定年前賃金の8割相当額の支払いを求めるXの請求をしりぞけ,また,Y社の定年後再雇用に向けた提案は不合理なものとまでは認め難いとして不法行為の成立も認めませんでした。
この判決をXが不服として控訴を申し立てたというのが今回の事案です。
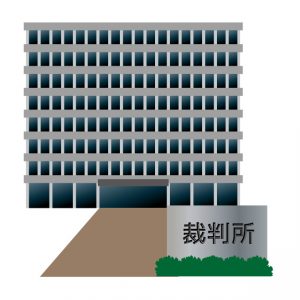 裁判所の判断
裁判所の判断
〇 Y社との間で定年後再雇用について労働契約が成立しているとのXの主張について
XとY社の交渉においてフルタイムかパートタイムかや賃金などの労働条件について合意に至っていないこと,就業規則では定年後再雇用の給与は,能力,技能,作業内容,学識・経験等を勘案して各人ごとに決定すると規定するにとどまっていて,就業規則等によってXの労働条件が自ずから定まることはないことなどから,XとY社との間で定年後再雇用に関する労働契約関係の成立を認めることはできない。
〇 本件提案が労働契約法20条に反するとのXの主張について
労働契約法20条は,有期労働契約を締結している労働者の労働契約の内容である労働条件について規定するもので,Xは,定年退職後,Y社と再雇用契約を締結したわけではないから,本件において少なくとも直接的には同条を適用することはできない。
仮に,有期労働契約の“申込み”についても同条が適用されるとしても,Y社の就業規則には賃金表は存在せず,パートタイム従業員もそれ以外の従業員も主たる賃金は能力・作業内容等を勘案して各人ごとに定めるものとされていて,パートタイム従業員とそれ以外の従業員との間で“契約期間の定めの有無”によって構造的に賃金に相違が生ずる賃金体系とはなっていないから,定年前の賃金と本件提案における賃金の格差が労働契約に「期間の定めがあることにより」生じたとは直ちには言えず,本件提案が労働契約法20条に違反するとは認められない。
〇 Y社が再雇用の条件として本件提案しか行わなかったことが不法行為となり得るか
高年法9条1項に基づく高年齢者雇用確保措置を講じる義務は,その趣旨・内容から,労働契約法制に係る公序の一内容を為しているというべきであるから,この法律の趣旨に反する事業主の行為は,上記措置の合理的運用により65歳までの安定的雇用を享受できるという労働者の法的保護に値する利益を侵害する不法行為となり得る。
雇用確保措置のうち継続雇用制度についても,定年の前後における労働条件の継続性・連続性が一定程度,確保されることが前提ないし原則となると解するのが相当であり,例外的に,定年退職前のものとの継続性・連続性に欠ける労働条件の提示が継続雇用制度の下で許容されるためには,同提示を正当化する合理的な理由が存することが必要である
〇 本件でY社の不法行為が成立するか
本件において月収ベースの賃金の約75パーセント減少につながるような短時間労働者への転換を正当化する合理的な理由があるとは認められず,Y社が本件提案をしてそれに終始したことは,継続雇用制度の導入の趣旨に反し,裁量権を逸脱又は濫用したものとして違法である
福岡高裁は,以上の判断を示して,Y社に対し,100万円の慰謝料の支払いを命じました。
 解説
解説
◇ 高年齢者雇用安定法が定める高年齢者雇用確保措置
「高年齢者等の雇用の安定等に関する法律」(以下,高年法と言います。)では,定年年齢を65歳未満に定めている事業主に対して,従業員の雇用を65歳まで確保する措置を講じることを求めています(高年齢者雇用確保措置。第9条)。
高年法の高年齢者雇用確保措置は,厚生年金の受給開始年齢が段階的に引き上げられ,男性の厚生年金・定額部分について2013年度から原則65歳とされたことに合わせて,2004(平成16)年の高年法改正時に,それまでの努力義務から法的義務とされ,内容としても,①定年年齢を65歳まで引き上げる,②65歳までの継続雇用制度を導入する,③定年制自体を廃止するの3つの選択肢からいずれかを選ぶ必要があると具体化されました。
また,高年齢者雇用確保措置のうち②の継続雇用制度については,平成25年3月までは労使協定で継続雇用制度の対象者を限定する基準を定めることが認められていましたが,平成24年の法改正により,平成25年4月以降は継続雇用の対象者を限定することができなくなり,希望者全員を継続雇用の対象としなければならなくなっています(*)。
* 平成25年3月迄に労使協定により継続雇用制度の対象者を限定する基準を定めていた事業主については,経過措置として,老齢厚生年金の報酬比例部分が支給されている労働者については,労使協定で定める基準により対象者を選定する制度を維持することが認められています(下図を参照)。
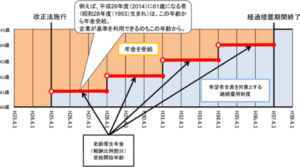
◇ 高年齢者雇用確保措置の導入状況
厚生労働省の平成28年「高年齢者の雇用状況」調査によれば,定年制を廃止するか(③)あるいは65歳以上の定年制とした企業(①)の割合は合計で18.7%にとどまっていて,3つある高年齢者雇用確保措置のうち,②の継続雇用制度を導入している企業の割合が大きくなっています。
また,継続雇用制度には,A)定年年齢に達した従業員をそのまま退職させずに雇用し続ける「勤務延長制度」と,B)定年年齢に達した従業員をいったん退職させた後,再び雇用する「定年後再雇用制度」の2つのタイプがありますが,後者の定年後再雇用制度を導入する企業が圧倒的に多くなっています。企業にとっては,再雇用制度を導入する方が,定年前の労働条件をいったんリセットして新たに労働条件を結び直すことができる,特に賃金を減額することができるという点でメリットがあると受けとめられているのだと思われます。
◇ 定年後再雇用の仕事内容と賃金
定年後再雇用制度を導入している企業では,定年後再雇用する従業員の仕事内容,賃金をどの様に設定しているのでしょうか。
独立行政法人労働政策研究・研修機構(JILPT)が平成24年改正法が施行された直後の平成25年7月から8月にかけて行った調査では,継続雇用者の仕事内容についての回答で最も多かったのは「定年到達時点と同じ仕事内容」で83.8%,年間給与については,定年到達時の水準を100とした場合,回答全体の平均値は68.3であったとされています(JILPT 改正高年齢者雇用安定法の施行に企業はどう対応したか-「高年齢社員や有期契約社員の法改正後の活用状況に関する調査」結果)。
つまり,定年の前後で仕事の内容は変えないが,賃金は約3割引き下げる,ということが一般的に行われている,ということになります。
◇ 本判決の意義
本件におけるY社の対応は,定年の前後においてXの賃金を年収ベースで約75%も切り下げ,また,Xがフルタイム勤務を希望しているにもかかわらず,週3日の短時間勤務しか提案しなかったというかなり“乱暴”なものでしたから,そうしたやや極端な事例についての判断であるということは念頭に置いておかなければなりませんが,定年後再雇用の賃金は大幅に引き下げられてもやむなしとする傾向がある中,福岡高裁判決は,そこに歯止めをかけた点で重要な意義があると言えます。特に,継続雇用制度について定年の前後における労働条件の継続性・連続性が一定程度確保されることを要求している点は注目されます。
この福岡高裁の判決については,X,Y社の双方が最高裁に上告を申し立てていましたが,今年3月,最高裁は上告を棄却する決定を下しました。判決が確定したことにより,定年後再雇用の労働者の賃金・労働条件を無限定に引き下げている企業や業界では,契約内容の見直しを含む対応が必要になると考えられます。
 コメント
コメント
本件でXは,Y社から示された再雇用の労働条件を最後まで受け入れなかったため,Y社との間で再雇用契約(有期契約)が結ばれることはありませんでした(Xは,黙示的な再雇用契約の成立を主張しましたが,裁判ではこの主張は認められませんでした)。このため,本件においては,平成25年の改正労働契約法で新たに導入された,同一の使用者と労働契約を締結している有期契約労働者と無期契約労働者との間で,期間の定めがあることによる不合理な労働条件の差別を禁止する同法第20条の規定の適用は直接には問題になりませんでした。
しかし,現在,本事案とは異なり,定年退職後に会社との間で嘱託契約(有期)を結んだが,正社員当時と業務の内容は全く変わっていないのに,賃金が約3割引き下げられてしまったというトラック運転手の事案が最高裁判所で争われており,そこでは労働契約法第20条の解釈適用が正面から問題になっています(長澤運輸事件)。4月20日に最高裁判所で弁論期日が開かれ,来月(6月)1日に判決が言い渡される予定と報じられています。“定年後再雇用においては仕事の内容が同一であっても定年前と比較して賃金を一定程度減額しても構わない”と言えるのか,仕事内容を変えずに賃金を引き下げるという手法が多くの企業で行われている実態が先行しているだけに,労働契約法第20条の均衡考慮原則について最高裁がどのような判断を示すのか,今から非常に注目されています。
【注目判例】 審判で命じられた面会交流が実行されなかった場合,間接強制をすることができるとした事例 ~最高裁第1小法廷:H25.3.28決定~
 事案の内容
事案の内容
Y(抗告人・母親)とX(相手方・父親)とは,裁判で離婚をした元夫婦です。平成22年に確定をした離婚訴訟の判決では,長女Aの親権者はYとされました。その後,Xは,Aとの面会交流を求めて家庭裁判所に調停,さらに審判を申し立てます。そして,平成24年5月,札幌家庭裁判所は,Yに対し,概ね以下のような要領(本件要領)でAとの面会交流を許さなければならないと命じる審判を出し,これが確定しました。
① 面会交流の日程・場所
・月1回,毎月第2土曜日の午前10時から午後4時まで
・Aの福祉を考慮してX自宅以外のXが定めた場所で行う
② 面会交流の方法
・Aの受渡場所はY自宅以外の場所とし,当事者間で協議して定めるが,協議が調わないときは,JR甲駅東口改札付近とする
・Yは,面会交流開始時に,受渡場所においてAをXに引き渡し,Xは,面会交流終了時に,受渡場所においてAをYに引き渡す
・Yは,Aを引き渡す場所のほかは,XとAの面会交流には立ち会わない
③ 代替日の調整
Aの病気などやむを得ない事情により上記①の日程で面会交流を実施できない場合は,XとYは,Aの福祉を考慮して代替日を決める
④ Xの学校行事への参列
Yは,XがAの入学式,卒業式,運動会等の学校行事(父兄参観日を除く。)に参列することを妨げてはならない
Xは,面会交流を命じたこの審判にもとづいて,平成24年6月,Aとの面会交流を行うことをYに求めました。しかし,Yは,AがXとの面会交流はしたくないという態度に終始していて,Aに悪影響を及ぼすとしてこれに応じませんでした。このため,Xは,同年7月,札幌家庭裁判所に対し,面会交流を認めた審判にもとづき,本件要領のとおりXがAと面会交流をすることを許さなければならないと命ずるとともに,Yがその義務を履行しないときは,YがXに対し一定の金員を支払うよう命ずる間接強制決定を求める申し立てをしました。
原審・札幌高裁決定(平成24年10月30日・民集67巻3号880頁)は,本件要領は,面会交流の内容を具体的に特定して定めており,また,Aが面会交流を拒絶する意思を示していることが間接強制をすることになじまない事情となることはないなどとして,Yに対し,本件要領のとおりXがAと面会交流をすることを許さなければならないと命じました。さらに,Yがその義務を履行しないときは,不履行1回につき5万円の割合による金員をXに支払うよう命じ,間接強制を認めました。
この札幌高裁の決定を不服としてYが申し立てた許可抗告に対する判断が,ここで紹介する最高裁決定になります。
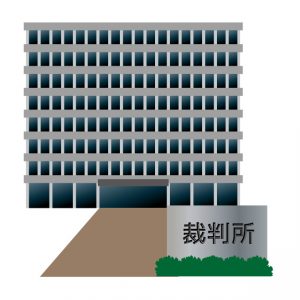 最高裁判所の判断
最高裁判所の判断
1 監護親に対し非監護親が子と面会交流をすることを許さなければならないと命ずる審判において,面会交流の日時又は頻度,各回の面会交流時間の長さ,子の引渡しの方法等が具体的に定められているなど監護親がすべき給付の 特定に欠けるところがないといえる場合は,上記審判に基づき監護親に対し間接強制決定をすることができる。
2 監護親に対し非監護親が子と面会交流をすることを許さなければならないと命ずる審判において,次のⅰ),ⅱ)のとおり定められているなど判示の事情の下では,監護親がすべき給付の特定に欠けるところはないといえ,上記審;判に基づき監護親に対し間接強制決定をすることができる。
ⅰ)面会交流の日程等は,月1回,毎月第2土曜日の午前10時から午後4時までとし,場所は,子の福祉を考慮して非監護親の自宅以外の非監護親が定めた場所とする。
ⅱ)子の受渡場所は,監護親の自宅以外の場所とし,当事者間で協議して定めるが,協議が調わないときは,所定の駅改札口付近とし,監護親は,面会交流開始時に,受渡場所において子を非監護親に引き渡し,子を引き渡す場面のほかは,面会交流に立ち会わず,非監護親は,面会交流終了時に,受渡場所において子を監護親に引き渡す。
 解説
解説
◇ 面会交流
離婚などで子どもと離れて暮らしている親(監護権を持っていない親=非監護親)が,子どもと直接会ったり,電話や手紙,メールやプレゼントの受け渡しを通じて子どもと定期的に交流することを「面会交流」といいます。
この非監護親の面会交流(権)については,平成23年の改正まで,民法の中にも明確な定めは置かれておらず,判例でその権利性が認められているにすぎませんでした。改正民法によって,夫婦が離婚する際,子の監護をする者,養育費などとともに「父又は母と子の面会及びその他の交流」について協議で定めること,協議が整わないときは家庭裁判所が定めることが規定されました(民法766条1,2項)。
家庭裁判所に面会交流を求める手続を申し立てるにあたっては,離婚の場合とは異なり,「調停前置」は要求されていません。このため,調停を経ずにいきなり審判の申し立てをするということも法律上は可能です。ただ,現実の運用としては,審判を申し立てても,まずは調停の手続に付されることが多いようです。
◇ 調停・審判における面会交流の取り扱い
最近の家裁の実務では,面会交流を禁止または制限すべき事由がなければ,原則として面会交流を行わせるという方向で調整が行われているのが実情です。
面会交流を禁止または制限すべき事由としては,例えば,ア)面会交流時に子どもが連れ去られるおそれがある場合,イ)非監護親が子どもに虐待をしていた場合,ウ)同居親が非監護親から暴力を振るわれていて,面会交流時に暴力が振るわれるおそれがある場合,エ)子ども自身が面会交流に拒絶的である場合などが挙げられます。
これらの事由の存否については,当事者の主張が大きく対立することも珍しくありません。家庭裁判所の調査官による調査を行うなどして,面会交流を禁止または制限すべき事由があるかどうかを見極めた上で,面会交流の実施することの適否を判断していくことになります。
今回の事案においても,審判手続の中でこうした面会交流を禁止または制限すべき事由の存否が争われたのですが,裁判所は面会交流を許さなければならないと判断しました。
◇ 裁判所による面会交流の実現手段
面会交流を実施する調停条項や審判条項があるにもかかわらず,監護親の非協力によりこれが実現できない場合,面会を求める非監護親としてどのような手段を取ることができるでしょうか。
1)履行勧告
面会交流を求める非監護親が取り得る最も簡便な手段は,『履行勧告』制度の利用です。非監護親からの申し出があると,まず,家裁調査官から,調停条項に定められた面会交流を実施するようにという文書が監護親に送付され,それでも反応がない場合には,電話をかけて履行を促すという仕組みになります。ただ,履行勧告はあくまでも“勧告”にとどまり,履行命令(家事事件手続法290条)のような強制力はありません。
2)損害賠償請求
監護親が面会交流に正当な理由なく応じないことが債務不履行(合意違反),もしくは不法行為となるとして損害賠償を求めるということも考えられ,実際に請求が認められている裁判例もいくつかあります(横浜地方裁判所平成21年7月8日判決・家庭裁判月報63巻3号など)。ただ,裁判の結論が出るまでにはどうしても一定の時間がかかってしまいます。
3)間接強制の申立て
そこで,次に考えられる手段が『間接強制』になります。間接強制とは,民事執行法が定める強制執行手続きの1つで,債務者に対して,一定の期間内に履行しなければその債務とは別に間接強制金の支払いを課すというものです。面会交流について間接強制を活用するということは,例えば,監護親に対して,「非監護親と子とを面会させよ。面会させない場合には,不履行1回につき金5万円を支払え」などという命令を裁判所に出してもらうということになります。
◇ 最高裁決定の意義
1)面会交流についても間接強制が許される
面会交流について間接強制手続を使うことができるかについては,これを肯定する見解が多数でしたが,否定説も有力に主張されていました。監護親の協力が得られないまま面会を強行することは,一般的に子の利益を害することになるとか,面会交流については監護親,非監護親との間に最小限の信頼関係があることが不可欠で,面会交流を強行することはこれを破壊することになるといった見解です。
今回の最高裁決定は,まず,こうした見解をしりぞけ,面会交流についても間接強制が許される場合があることを明らかにしました。
2)給付内容の特定について
間接強制を含む強制執行を裁判所が命ずるには,債務者が履行しなければならない債務の内容が特定していなければなりません。したがって,調停や審判で面会交流を行うことが認められていても,当事者間での協議や事前の調整が必要となるような定め方になっていると,裁判所に間接強制を命じてもらうことは難しくなります。
面会交流の場合,給付内容がどの程度まで特定していれば間接強制を命じることができるかについて,今回の最高裁決定は,「面会交流の日時又は頻度,各回の面会交流時間の長さ,子の引渡しの方法等が具体的に定められているなど監護親がすべき給付の特定に欠けるところがないといえる場合は,上記審判に基づき監護親に対し間接強制決定をすることができると解するのが相当」と判断しました。
実は,最高裁は,同じ日に本件を含む3つの事案について面会交流に関する間接強制の許否の判断を示していて,他の2つの事案については間接強制を否定しています。審判に子の引き渡しに関する規定がないこと,面会時間についての調停条項の定め方が延長の余地があるものとされていることがそれぞれ理由とされています。間接強制が必要となることが予想されるようなケースにおいては,「面会交流の日時,頻度」「面会実施時間の長さ」「子の引き渡し方法」については具体的に決めておく必要がある,ということになります。
3)調停,審判の後に生じた事情の取り扱いについて
本件事案でYは,審判後,Aが面会交流を拒絶する態度に終始していることを面会交流を拒絶する正当事由として主張していました。審判(調停)の時とは異なる状況が生じたといえる場合であっても間接強制を命じることができるのでしょうか。
この点について最高裁は,「審判時とは異なる状況が生じたといえるときは上記審判に係る面会交流を禁止し,又は面会交流についての新たな条項を定めるための調停や審判を申し立てる理由となり得ることなどは格別,上記審判に基づく間接強制決定をすることを妨げる理由となるものではない」と判断しました。つまり,面会交流を定める審判や調停の後に状況が変わった場合には,改めて調停や審判を申し立てるなどして面会交流に関するルールの変更を求めればよく,非監護親が申し立てた間接強制を却下するということにはならないとしたのです。
 コメント
コメント
本件を含む3件についての最高裁決定によって,面会交流が拒まれている事案について間接強制を命じることができる場合があることが明らかになり,しかも,間接強制を求める場合,審判・調停においてどの程度まで給付内容を特定しておく必要があるのかの判断の基準も示されました。もう5年前の決定になりますが,その後,この最高裁決定は,面会交流に関する家裁の実務に非常に大きな影響を与えています。非監護親の側からは,この最高裁決定を意識して,面会交流の具体的な内容を調停条項の中に取り込んで欲しいという要望が出されることが多くなり,その結果,調整が難航するというケースも増えてきました。ただ,当事者間に最低限の信頼関係がないと面会交流を円滑に実施することは難しいため,少なくともスタート時には協議・調整が必要となってくる事案も少なくありません。間接強制の発令以前にどのように面会交流の履行を促進・確保していくかは,依然として大きな課題です。
【注目判例】前頭側頭葉型認知症(FTD)にり患していた男性の万引き行為について無罪が言い渡された事例 ~大阪地裁:H29.3.22判決~
 【事案の内容】
【事案の内容】
過去,万引きで有罪判決を3回受けたことがあり,直近前科で執行猶予の付された判決を受け,その猶予期間中であった事件当時70歳の男性が,平成27年12月28日,大阪市内の商店で漬物2点(500円相当)を万引きし,窃盗罪で起訴をされたという事案について,大阪地方裁判所が無罪を言い渡したケースです。
男性は,平成19年4月に脳梗塞を発症した後,年金と生活保護を受給しながら妻と2人で生活していました。平成22年5月,平成26年3月の2度,スーパーで万引きをして略式の罰金刑を受けており,さらに,平成27年10月にも同様の万引きの事案で懲役1年,執行猶予3年の有罪判決を受けていました。執行猶予付き判決を受けた1ヶ月後の平成27年11月には中等度ないし軽度の認知症と診断され,妻は男性に一人で買い物に行くことを禁じていましたが,散歩や図書館に出かけるなどしたとき,食料品を万引きする行為を繰り返していたようです(妻が知る限りでも3回あり,商品を買い取るなどして事件化することを防いでいたようです)。
事件当日,男性は,図書館などに行くためと妻に告げて自転車で家を出たのですが,午前10時40分頃,商店で本件の万引きをしました。犯行時,被害品が並べられていた陳列台のすぐ脇には店主が椅子に座って店番をしていたのですが,男性は,店主の目の前で商品を両手でつかみ,そのまま店を出ました。店主が「お金は」などと声をかけたのですが,男性は,そのまま自転車に乗って走り始め,店から85mの地点で追いかけてきた店主の息子に肩をつかまれ,特に抵抗することもなくその場に座り込み,逮捕されました。所持品には,別のスーパーで万引きをした値札シールのはがされたステーキ肉(2枚入り)2パックが入っていました。
本事案の争点は,男性が事件当時,認知症の影響によって行為の違法性の弁識や行動の制御が不可能な状態(心神喪失状態)に陥っていたと言えるかです。
 【裁判所の判断】
【裁判所の判断】
〇 直近前科の懲役刑の執行猶予期間中にあり,妻から単独での買い物を禁止されるなどし,当日も妻が家で昼食の準備をしている中で,老夫婦2人分をはるかに超える量のステーキ肉や漬物を盗むという本件当日の被告人の行動は,同認知症の影響を考慮しないと合理的な説明ができず,同認知症が発症した可能性のある時期以前の被告人には本件のような万引き等の問題行動はみられず,発症の前後で明らかな懸隔が認められることも併せみると,本件当時の被告人につき,事理弁識能力ないし行動制御能力が著しく減弱していたのはもとより,これらの能力を欠いていた疑いは合理的に否定できない。
→ 裁判所は,被告人が本件当時前頭側頭葉型認知症(FTD)の影響によって心神喪失の状態に陥っていた可能性を合理的に否定することができないとし,被告人に無罪を言い渡しました。
 【解説】
【解説】
◇ 刑事責任能力
人が刑罰法規に触れるような行為をした時,その人物に対し事件の責任を問うことができるか(刑罰を科すことができるか),刑事責任能力があると言えるかが問題となります。刑事責任能力は,事物の是非・善悪を弁別し(事理弁識能力)と,それに従って行動する能力(行動制御能力)とからなり,この能力を欠いてしまっている人に対しては,その行為を非難することができないため,刑罰を科すことはできません。
日本の刑法は,刑事責任能力が完全に損なわれている場合を「心神喪失(シンシンソウシツ)」と称して刑罰を科すことはできないとし,著しく減退している場合を「心神耗弱(コウジャク)」と称して刑の減軽事由としています(刑法第39条)。
〔刑法第39条〕
心神喪失者の行為は罰しない
心神耗弱者の行為はその刑を減軽する
◇ 刑事責任能力の判断
行為者の刑事責任能力を判断するには,その前提となる“生物学的要素”と“心理学的要素”を評価することになります。“生物学的要素”の評価とは,わかりやすく言うと精神疾患・精神障害があるかどうかの判断,“心理学的要素”の評価とは,事理弁識能力,行動制御能力の有無・程度についての判断となります。
刑事責任能力の有無を判断するのは最終的には裁判官です。ただ,裁判官は必ずしも精神医学の知識を持っているわけではありません。このため,精神科医に依頼をして鑑定が行われることもあります(精神鑑定)。しかし,精神鑑定が実施された場合であっても,刑事責任能力に関する判断はあくまで法律判断であるため,精神鑑定の結果をどう評価するかは裁判官に委ねられていることになります(S58.9.13 最高裁第3小法廷決定)。
◇ 認知症と刑事責任能力
刑事責任能力が問題となる疾患として典型的なものは統合失調症です。統合失調症では,幻覚,妄想によって行動が支配されて行動制御能力が減退することがあり,この点が認められれば,制御能力が損なわれた程度に応じて心神喪失,心神耗弱が認定されることになります。また,万引きとの関係でしばしば問題となる疾患としては,クレプトマニア(窃盗壁)があります。クレプトマニアは,経済的な利益を得るためではなく,窃盗それ自体への衝動から盗みを繰り返してしまうという精神障害の一種で,この疾患があると,特に行動制御能力に影響が生じると考えられています。
これに対し,本件の男性のような“認知症”については裁判例の集積が乏しく,責任能力を欠くとして無罪とされた事例はほとんどありませんでした。
判決は,鑑定医の判断を踏まえ,“前頭側頭葉型認知症”(Fronto Temporal Dementia)にり患していた男性が,この疾病の影響によって,「買い物をして帰宅するという過去の習慣的行動が自動化した状態に陥り,被害店舗前で漬物が際立って見えると,執行猶予期間中であるなどの現状認識を持つことができないまま漬物を手に取り,清算の段取りを飛ばしてそのまま帰宅しようとして本件犯行を犯したとみることができる」と認定し,本件当時の男性について,「事理弁識能力ないし行動制御能力が著しく減弱していたのはもとより,これらの能力を欠いていた疑いは合理的に否定できない」と無罪を言い渡したものです。
 【コメント】
【コメント】
認知症には,一般によく知られているアルツハイマー型認知症のほかに,レピー小体型認知症,脳血管性認知症,男性がり患していた前頭側頭葉型認知症(FTD)などがあります。前頭葉は思考や感情表現,判断をコントロールする部位,側頭葉は聴覚,味覚,さらには記憶,感情をつかさどる部位とどちらも非常に重要な器官です。この部位が委縮し,血流が低下することによって様々な症状を呈することになるのですが,アルツハイマー型やレビー小体型などと比べると,記憶の障害は目立たないのに対し,人格の変化や非常識な行動などが目立つとされているようです。
刑事責任能力に関する判断は,前述したように,あくまで法律判断ですから,FTDにり患しているというだけで心神喪失,心神耗弱と認定されるわけではなく,犯行時に取られた行動,犯行についての弁解内容,捕まった時の様子,普段の生活状況なども踏まえて総合的に判断されるものです。その意味であくまで事例判断ではありますが,FTDが事理弁識能力,行動制御能力を大きく損なうことがあることを明らかにした点で注目される判決と言えます。
【注目判例】マンション管理組合の理事長を理事会決議によって解任することの可否 ~平成29年12月18日・最高裁判決~
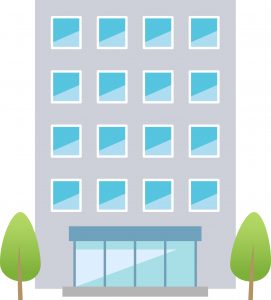
事案の内容
マンションの管理組合(被上告人・X)の理事長だった男性(上告人・Y)が,他の理事からの反対があったにもかかわらず,理事会の決議を経ないまま,管理会社を変更する案件を総会に諮ろうとし,臨時総会を招集する手続をとりました。これに対し,Yに反対する11名の役員は,理事会で,Yを理事長から理事に役職を変更し,別の理事Aを新たな理事長に選びました(本件理事会決議)。実際の事案では,この理事会決議の後,Yに反対する役員らは,Yを理事からも解任することを議題とする臨時総会を招集するようA理事長と管理組合(X)に請求し,これに対抗するYが理事長として別に臨時総会を招集するという非常に込み入った経過を辿るのですが,ここでは省略します。 この管理組合の規約においては,役員の選任及び解任については総会の決議を経なければならないという規定が置かれている一方,役員の選任については,「理事・監事は組合員のうちから総会で選任する」「理事長・副理事長等は理事の互選により選任する」という規定となっていました。Yは,役員の解任手続に直接触れた規定は前者しかないことから,理事会の決議によっては理事長職を解くことはできないと主張したのに対し,管理組合(X)側は,理事会で理事長を“理事の互選により選任”できるということは,これに準じて“解任”もできると解釈してよいと主張しました。 1審の福岡地方裁判所久留米支部判決は,「規約上,理事長を含む役員の解任は総会の議決事項」であるとして理事会の決議では解任できないと判断。2審の福岡高裁判決も1審の結論を支持しました。この1・2審の判断を不服として管理組合(X)側が上告したのが本件事案です。
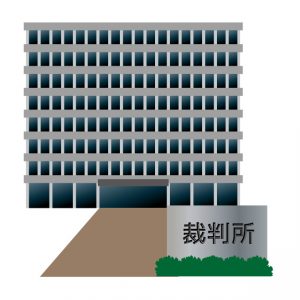
最高裁判所の判断
〇 理事を組合員のうちから総会で選任し,理事の互選により理事長を選任する旨の定めがある規約を有するマンション管理組合において,その互選により選任された理事長につき,理事の過半数の一致により理事長の職を解くことができる
→ 管理組合(上告人・X)側の主張を認め,2審の福岡高裁判決を破棄し,審理を福岡高裁に差し戻しました。
 解説
解説
マンション管理組合の運営をめぐっては,管理会社の選定・変更,大規模修繕工事の施工業者の選定などで組合員の中に意見の対立が生じ,それが役員の解任劇にまで発展してしまうということがあります。本事案も,管理会社の変更をめぐる役員間の対立がエスカレートしたもののようです。
◇ 役員の選任,解任に関連する区分所有法の規定内容
マンション管理組合の理事長の選任,解任の手続について,建物の区分所有等に関する法律は,“…規約に別段の定めがない限り,集会の決議によって,管理者を選任し,又は解任することができる”と規定しています(同法第25条1項。ここで「集会」はマンションでは管理組合の総会,「管理者」は理事長を指すと解して差し支えありません)。つまり,管理規約に特に定めがなければ,総会の決議によって理事長の選任,解任を行うということになります。
◇ 役員の選任,解任に関連する標準管理規約の規定内容
では,マンションの管理規約はどうなっているのか。実は,マンションの管理規約については,国土交通省がモデルとなる標準管理規約というものを作っています(国交省のHPにアップされていますので,関心がある方はご覧ください)。この標準管理規約では,理事長など役員の選任,解任の手続きを次のように定めています(本件事案当時のもの。現在の文言は,その後の改正によって若干修正されています)。
【標準管理規約】
第35条 管理組合に次の役員を置く。
一 理事長
二 副理事長 ○名
三 会計担当理事 ○名
四 理事(理事長,副理事長,会計担当理事を含む。以下同じ。) ○名
五 監事 ○名
2 理事及び監事は,組合員のうちから,総会で選任する。
3 理事長,副理事長及び会計担当理事は,理事の互選により選任する。
つまり,標準管理規約では,総会では“理事・監事を誰にするか”だけを決め,監事以外の役職(理事長,副理事長,会計担当理事)を誰に担当させるかについては,理事が話し合って決めるという仕組みになっていることになります。 そして,多くの管理組合では,国交省の標準管理規約に準拠した管理規約が作られていて,実際,本件事案のX管理組合の管理規約も,同様の内容になっていました。
◇ 理事会決議による理事長解任の可否
さて,標準管理規約と同じ内容の規約があるマンション管理組合において,多数の理事が,理事長(本件事案では「Y」)を不適任で辞めさせたいと考えるようになった場合,総会を開かずに,理事会の決議によって何らかの対応をすることができるでしょうか。 まず,Yを理事会決議によって理事から外してしまうということは,標準管理規約第35条2項に反することになるので,これはできません。 次に考えられるのが,本件事案でX管理組合がした対応になりますが,Y理事長を理事長からヒラ理事にいわば“降格”するという対応です。管理規約に“理事会決議により理事長職を解任することができる”などといった規定を設けていれば,こうした対応も問題なくできるということになりますが,標準管理規約と同様の規定しか置いていない場合については,消極,積極の両説がありました。 消極説は,標準管理規約の第35条3項は,理事長を理事の互選によって選任するおきの規定であり,「解任」について定めたものではないと条文の文言を重視します。本事案の1審,2審判決は,この消極説に立つものでした。 これに対し,今回の最高裁判決は,標準管理規約と同じ内容となっているX管理組合の管理規約の規定について,「理事長を理事が就く役職の1つと位置付けた上,総会で選任された理事に対し,原則として,その互選により理事長の職に就く者を定めることを委ねるものと解される。そうすると,このような定めは,理事の互選により選任された理事長について理事の過半数の一致により理事長の職を解き,別の理事を理事長に定めることも総会で選任された理事に委ねる趣旨と解するのが,本件規約を定めた区分所有者の合理的意思に合致するというべきである」として,積極説に立つことを明らかにしました。
 コメント
コメント
取締役会を置く株式会社では,代表取締役を取締役会決議によって解任することができるとされています(会社法362条2項2号)。このため,代表取締役が,突然,取締役会で解任をされるという“クーデター”のようなことが起こることになります。会社の代表者を適時,迅速に交代できるようにしておくことが,企業経営上好ましいという考え方に基づくものです。 今回の最高裁判決は,こうした考え方をマンションの管理組合にも及ぼしたものと言えます。役職者の交代を理事会で決められるようにすることで,管理組合の運営を円滑に行えるようにする狙いがあるのかもしれません。ただ,理事会にこうした権限が認められるとなると,役員間の対立が理事会に持ち込まれてしまい,逆に,管理組合の運営が不安定になるということも起きかねません。 今回の最高裁判決を受けて,おそらく標準管理規約も改訂されることになるのだと思われますが,みなさんのマンションの管理組合規約を標準管理規約に習って改訂するかについては,そのメリット・デメリットをよく議論して,慎重に対応することが望ましいと思います。

【注目判例】NHK受信料訴訟・最高裁大法廷平成29年12月6日判決
事案の内容
NHK(日本放送協会)が受信契約の申し込みに応じない男性に対して受信料の支払いを求めた事件の最高裁判決です。男性は,2006年3月,自宅にテレビを設置し,5年半後の11年9月にNHKから受信契約を結ぶよう求められたのですが,その後も受信契約を結ばず,受信料の支払いをしていませんでした。このため,NHKは同年11月,この男性に対し,受診料の支払いを求める裁判を起こしました。1審,控訴審ともに,設置者に受信契約を義務づける放送法64条の規定は憲法に違反せず,NHKが契約を求める裁判を起こして確定した時に契約が成立し,テレビなどを設置した時までさかのぼって支払い義務が生じるという判断を示していました。男性が最高裁に上告し,この度(12月6日),最高裁の大法廷判決が言い渡されました。
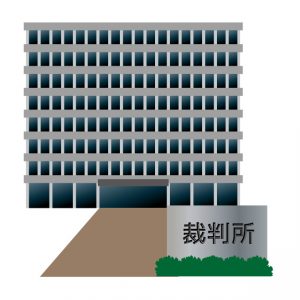 最高裁判所の判断
最高裁判所の判断
〇 放送法64条1項は,受信設備設置者に対し受信契約の締結を強制する旨を定めた規定であり,NHKからの受信契約の申込みに対して受信設備設置者が承諾をしない場合には,その者に対して承諾の意思表示を命ずる判決の確定によって受信契約が成立する
〇 受信契約の申込みに対する承諾の意思表示を命ずる判決の確定により受信契約が成立した場合,同契約に基づき,受信設備の設置の月以降の分の受信料債権が発生する
〇 受信契約に基づき発生する受信設備の設置の月以降の分の受信料債権の消滅時効は,受信契約成立時から進行する
〇 放送法64条1項は,同法に定められた日本放送協会の目的にかなう適正・公平な受信料徴収のために必要な内容の受信契約の締結を強制する旨を定めたものとして,憲法13条,21条,29条に違反しない
 解説
解説
◇ テレビの視聴者はNHKに受信料を支払っています。放送法第64条1項は,「協会の放送を受信することのできる受信設備を設置した者は,協会とその放送の受信についての契約をしなければならない」としていて,受信料の支払義務は,形式的にはNHKと受信契約を結ぶことによって生じることになっています。そうすると,NHKと受信契約を結ばずにいれば受信料を支払わなくてすむのでしょうか。放送法第64条1項は,受信設備の設置者に受信契約を締結する私法上の義務を課したものと言えるのでしょうか。
この放送法の規定の捉え方については,契約締結に向けて自発的協力をすべき国民の努力義務を定めたに過ぎないとする学説もあります。しかし,今回の最高裁判決は,「放送法64条1項は,原告(※NHK)の財政的基盤を確保するための法的に実効性のある手段として設けられたものと解されるのであり,法的強制力を持たない規定として定められたとみるのは困難」だとして,テレビ(受信設備)を設置した者がNHKと受信契約を締結することはこの放送法の規定による私法上の義務であるとしました。
◇ 次に,放送法第64条1項によりテレビの設置者にNHKと受信契約を結ぶ義務があるとして,受信契約は,いつ,どのような形で成立することになるのでしょうか。
この裁判で,NHK側は,NHKがテレビの設置者に受信契約の締結を申し込んだ時点で受信契約は成立するという主張をしていました。この事案で言えば,2011年9月にNHKが男性に受信契約の締結を申し入れた時点で受信契約は成立したことになるという主張です。しかし,今回の最高裁判決は,放送法は「任意に受信契約を締結しない者について契約を成立させる方法につき特別な規定を設けていないのであるから,任意に受信契約を締結しない者との間においても,受信契約の成立には双方の意思表示の合致が必要」であるとして,このNHK側の主張をしりぞけました。
“意思表示の合致”が必要ということになると,契約を結ぶことを拒んでいる人との間では,いつ,どのような形で“意思表示の合致”があることになるのか,受信契約が結ばれたことになるのかが次に問題となります。最高裁は,「放送法64条1項は,受信設備設置者に対し受信契約の締結を強制する旨を定めた規定であり,原告からの受信契約の申込みに対して受信設備設置者が承諾をしない場合には,原告がその者に対して承諾の意思表示を命ずる判決を求め,その判決の確定によって受信契約が成立すると解するのが相当」と判断しました。つまり,受信契約を成立させて受信料を徴収するには,NHKは,契約締結を拒んでいる人に対して受信契約締結の承諾の意思表示を命ずる裁判を起こし,勝訴判決を確定させる必要があるということになります。
◇ NHKの勝訴判決が確定した時に受信契約が成立するとなると,受信料もこの時から支払えばよいということになりそうにも思えます。
放送法には,受信契約の締結義務を定めた先ほどの第64条の規定はあるのですが,受信料の支払義務が生じる時期(=受信料債権が発生する時期)を定めた規定はありません。他方,NHKの「放送受信規約」(※ 約款のようなもの)には,「受信機の設置の月から…(中略)…放送受信料を支払わなければならない」とする規定が置かれています(第5条第1項)。受信契約の内容をNHKが一方的に作成する受信規約で定めることの可否も争点となったのですが,今回の最高裁判決は,「適正・公平な受信料徴収のために必要なもの」「適正・公平な受信料徴収のために必要な範囲内」のものであれば放送受信規約で定めることはでき,さらに,「同じ時期に受信設備を設置しながら,放送法64条1項に従い設置後速やかに受信契約を締結した者と,その締結を遅延した者との間で,支払うべき受信料の範囲に差異が生ずるのは公平とはいえないから,受信契約の成立によって受信設備の設置の月からの受信料債権が生ずるものとする上記条項は,受信設備設置者間の公平を図る上で必要かつ合理的」であるとして,受信料の支払義務は,NHKの勝訴判決が確定した時ではなく,テレビ(受信設備)の設置の月から生ずるとしました。
◇ 受信料の支払義務がテレビ(受信設備)の設置の月からということになると,この受信料債権の消滅時効期間(※ 定期給付債権として“5年”とされています)も,このテレビ設置の月からカウントされることになるのでしょうか。
この点について,最高裁は,「消滅時効は,権利を行使することができる時から進行する(民法166条1項)ところ,受信料債権は受信契約に基づき発生するものであるから,受信契約が成立する前においては,原告は,受信料債権を行使することができない」として,受信料債権の消滅時効は受信契約成立時から進行すると判断しました。
 コメント
コメント
受信料の不払いはNHKの不祥事が相次いだ2004年頃から急増し,2006年度の支払率は70%を切るところまで落ち込みました。このため,NHKは,受信料の徴収を強化するようになり,契約に応じないテレビ設置者に対して訴訟を提起するということも積極的に行うようになっています。今回の最高裁判決が出るまでに,多くの下級審の裁判例が積みあげられてきました。この事件については,最高裁が事件を大法廷に回付して判断を示すことになったため,非常に注目を集めました。しかし,結論から言えば,特に驚くような判断は示されなかったということになるかと思います。放送法第64条がテレビの設置者に受信契約締結の義務を課しているということが確認され,また,受信契約の締結を拒むものとの間でNHKが契約を成立させるには勝訴判決の確定が必要になるという判断が示されたことにより,今後,NHKがさらなる受信料の徴収強化を進めることが予想されます。放送法の制定は今から60年以上も前のことで,当時は地上波放送のみ,民放も限られていました。現在,NHKは地上波2波,BS3波と5チャンネルを保有する巨大メディアとなり,他方で,スクランブル放送のような視聴者にだけ課金するような技術もできています。公共放送のあり方については,こうした時代の変化を踏まえた様々な議論があるところですが,今回の最高裁判決は,受信料裁判を梃子にして公共放送の改革を求めることには限界があるということを示しているとも言えます。
