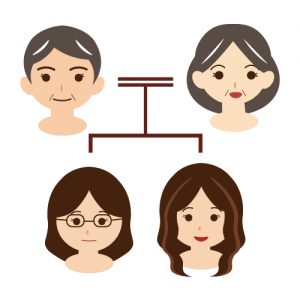 事案の概要
事案の概要
上告人Xは,被上告人Yとともに,B(父)・A(母)夫婦の子です。B・A夫婦の間には,もう一人の実子C,さらに,B・A夫婦と養子縁組をしたYの妻Dがいます。このような親族関係の下,まず,Bが平成20年12月に死亡しました。亡Bの遺産をめぐって遺産分割調停が申し立てられ,分割合意が成立する前に,Aと養子Dの二人は,それぞれ自分の相続分をYに無償で譲渡して調停手続から脱退しました(A,Dの手続からの脱退により,亡Bの遺産については,X,Y,Cの3者間において遺産分割調停手続が進められ,平成22年12月に遺産分割調停が成立しました)。その後,Aは,平成22年8月,全財産をYに相続させる旨の公正証書遺言を作成しました。
亡Bの遺産相続をめぐって以上のような経緯があった後,平成26年7月,今度はAが亡くなりました。死亡時,Aには介護費用の債務とほぼ同額のわずかな預金しかありませんでした。しかし,Aは,前述の通り,生前,Bの相続分を無償でYに譲渡しています。この相続分の無償譲渡は民法903条1項が規定する贈与にあたり,これによって自己の遺留分が侵害されているとして,XがYに対して遺留分減殺請求を行ったというのが本件事案になります。
原審・東京高等裁判所(平成29年6月22日判決)は,ア)相続分の譲渡による相続財産の持分の移転は,遺産分割が終了するまでの暫定的なものであり,最終的に遺産分割が確定すれば,その遡及効によって,相続分の譲受人は相続開始時に遡って被相続人から直接財産を取得したことになるから,譲渡人から譲受人に相続財産の贈与があったとは観念できない,イ)相続分の譲渡は必ずしも譲受人に経済的利益をもたらすものとはいえず,譲渡に係る相続分に経済的利益があるか否かは当該相続分の積極財産及び消極財産の価額等を考慮して算定しなければ判明しないなどとして,本件相続分譲渡は,その価額を遺留分算定の基礎となる財産額に算入すべき贈与(民法1044条,903条1項)には当たらないと判断し,Xの請求を斥けました。
今回は,Xの上告受理申し立てに対して最高裁が示した判断を紹介したいと思います。
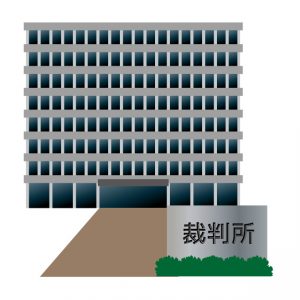 裁判所の判断
裁判所の判断
〇 共同相続人間においてされた無償の相続分譲渡は民法903条1項に規定する「贈与」にあたるか
「相続分の譲渡は、譲渡に係る相続分に含まれる積極財産及び消極財産の価額等を考慮して算定した当該相続分に財産的価値があるとはいえない場合を除き、譲渡人から譲受人に対し経済的利益を合意によって移転するものということができ」,「遺産の分割が相続開始の時に遡ってその効力を生ずる(民法909条本文)とされていることは,以上のように解することの妨げとなるものではない」から,共同相続人間においてされた無償による相続分の譲渡は,譲渡に係る相続分に含まれる積極財産及び消極財産の価額等を考慮して算定した当該相続分に財産的価値があるとはいえない場合を除き,上記譲渡をした者の相続において,民法903条1項に規定する「贈与」に当たる。
 解説
解説
◇ 遺留分について
「遺留分」とは,兄弟姉妹以外の法定相続人について法律で保障されている最低限度の相続分といいます。被相続人が法定相続人にとって非常に不公平,不平等な遺言や生前贈与をした場合,この遺留分の限度で,遺産の一部を取り戻すことができるという仕組みです。遺留分が保障されている法定相続人(遺留分権利者と言います。)は,①配偶者,②子ども,③父母・祖父母など直系尊属です。②の子どもには,実子だけでなく養子も含まれますし,子がすでに亡くなっている場合の代襲相続人にも遺留分が認められます。他方で,被相続人の兄弟姉妹は,第3順位の法定相続人ですが,法律上,遺留分は認められていません(民法1028条)。相続財産に対する遺留分全体の割合は,原則として2分の1です。直系尊属(父母,祖父母)だけが相続人となるというパターンのときだけ,例外として3分の1が遺留分となります。遺留分権利者が複数いる場合には,この遺留分割合を各相続人の法定相続分で配分します。
本件の事案は,子どものみが相続人となるケースとなるので,相続財産に対する遺留分全体の割合は2分の1となります。そして,Aの子は,X,Y,C,Dの4名いますから,各自の遺留分は1/8(1/4×1/2)ということになります。
◇ 遺留分の基礎となる財産
遺留分を計算するには,まず,遺留分の基礎となる財産を確定させる作業が必要になります。
遺留分は,「被相続人が相続開始の時において有した財産の価額にその贈与した財産の価額を加えた額から債務の全額を控除して,これを算定する」とされています(民法1029条)。つまり,ア)相続開始時に現存している財産に,イ)生前に贈与した財産を加え,そこから,ウ)債務を差し引いたものが,遺留分を計算する際の基礎となる財産ということになります。
イ)の「生前に贈与した財産」にどこまでの範囲のものが含まれるかについては,相続人以外の第三者に贈与した財産と,相続人に生前贈与した財産とに分けてみておく必要があります。相続人以外の第三者に贈与した財産については,原則として,相続開始前1年以内に贈与されたものに限って遺留分算定の基礎となる財産に算入するということになっています。但し,1年以上前に贈与したものであっても,贈与当事者の双方が遺留分権利者に損害を加える結果となることを知って贈与したものは,基礎となる財産に算入することになります(民法1030条)。これに対し,相続人に生前贈与した財産については,それが民法903条1項が規定する『特別受益』に該当する贈与といえる場合には,1年以上前の贈与であったとしても,遺留分を計算する際の基礎となる財産に含めることとされています(最高裁平成10年3月24日判決)。なお,特別受益にあたらない贈与については,民法1030条に従って処理されることになります。
◇ 特別受益とは?
特別受益に該当する贈与とはどのようなものでしょうか。この点について民法は,「共同相続人中に,被相続人から,遺贈を受け,又は婚姻若しくは養子縁組のため若しくは生計の資本として贈与を受けた者があるとき」を特別受益としています(903条1項)。「遺贈」とは遺言によって遺産を無償で他人に譲渡することです。特定の相続人に遺贈を行うとすべて特別受益になります。「婚姻若しくは養子縁組のために受けた贈与」は,“持参金”,“支度金”といったものがこれに該当します。「生計の資本として受けた贈与」としては,例えば,子どもが独立をした時に贈与した不動産,あるいは不動産の購入費用などが典型的なものとなります。子どもの学費については,高校の学費までは親の子に対する扶養義務履行の範囲内とされ,特別受益にはあたりません。 特別受益にあたる贈与があるケースでは,贈与による利益を受けた相続人(受益者)から相続分を減額することになります。減額の方法として,特別受益の持ち戻し計算というものを行います。これは,死亡時に残された遺産に受益者が受けた贈与分を加えて“みなし相続財産”というものを想定し,ここから法定相続分に従って遺産配分をするという計算方法になります。こうした特別受益の制度は,生前贈与や遺贈をした被相続人の意思を尊重しつつも,生前贈与や遺贈の「持ち戻し」をすることにより,法定相続分に修正を加えて相続人間の実質的な公平を保とうとする仕組みになります。
◇ 相続分の無償譲渡は民法903条1項の特別受益に該当する贈与にあたるのか
特別受益の仕組みを規定している民法903条1項の条文は,先ほど見ていただいたように「贈与を受けた者」となっているので,相続分を無償で譲り受けた者をこれと同じに扱うべきかについては争いがあり,下級審の裁判例も結論が分かれていました。本件の原審(東京高等裁判所・平成29年6月22日判決)は,冒頭で述べたようにこれを消極的に解した訳ですが,同じ東京高等裁判所の別の判決では,相続分の無償の譲渡によって「財産的価値の増加があるのであるから,相続分の譲渡についても特別受益としての生計の資本の贈与に該当し得る」と本件原審とは異なる判断が示されていました(東京高裁・平成29年7月6日判決:判例時報2370号31頁)。最高裁がどちらの解釈を支持するか注目されていた訳ですが,相続分の無償譲渡は原則として民法903条1項の特別受益にあたる,ただ,譲渡に係る相続分に含まれる積極財産及び消極財産の価額等を考慮して算定した当該相続分に財産的価値があるとはいえない場合は例外的に特別受益にはあたらない,という判断基準が示されたのです。
 コメント
コメント
今回の最高裁判決により,相続分の無償譲渡は原則として特別受益に該当するということになったので,相続分の譲渡を検討する際には,相続人となることが予定される者の遺留分を侵害することがないかを考慮する必要があります。また,今回の事例は共同相続人の間で相続分の譲渡が行われたというものでしたが,遺産分割協議や遺産分割調停によってBの遺産に関するAの法定相続分をYに取得させるという合意が成立することもあります。その場合,やはり特別受益の問題が生じることになるのかは残された課題となります。
