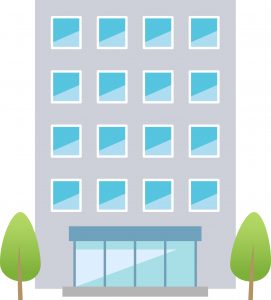事案の概要
事案の概要
甲銀行は,乙会社に貸金等の返還を求めるにあたり,乙社の貸金等返還債務の連帯保証人となっていたA(X2の叔父)らに対し,連帯保証債務の履行として8000万円の支払いを求める訴訟を提起し,平成24年6月7日,甲の請求を認容する判決が言い渡され,その後,この判決は確定しました。判決言渡し直後の同月30日,Aが死亡し,相続人であったAの妻,子2人は,同年9月までに家庭裁判所に相続放棄の申述をして受理されました。この結果,Aの兄弟姉妹およびその代襲相続人(亡くなった兄妹姉妹の子)の合計11名がAの法定相続人となったのですが,このうちB(Aの弟でX2の父親)は,平成24年10月19日,自分がAの相続人となったことを知らないまま,したがって,相続の承認あるいは放棄の手続をとらないまま,死亡してしまいました。Bの法定相続人は,妻X1と二人の子(X2ほか1名)です。
甲銀行から平成27年6月に上記の確定判決にかかる債権を譲り受けたY社は,同年11月,X1,X2について,その相続分の範囲で強制執行することができる旨の承継執行文の付与を受け,これが同月11日,X2に送達されて,X2は初めて父BがAの相続人になっていたこと,自分がBからAの相続人としての地位を承継していたことを知りました。さらに,Y社は,平成28年1月12日,Bが所有していた不動産について相続による所有権移転登記を代位により経由した後,この不動産について強制競売の申し立てを行いました。そこで,X2は,X1とともに,平成28年2月5日,Aからの相続について家庭裁判所に相続放棄の申述を行い(同月12日にこの申述は受理),さらに,同月23日,相続放棄をしたことを異議事由として,Y社の強制執行を許可しないことを求める「執行文付与に対する異議の訴え」(民事執行法34条)を提起しました(なお,X1は,第1審で相続放棄の再抗弁を撤回しています)。
原審は,“再転相続”が生じた場合の再転相続人の熟慮期間を定めた民法916条の「その者の相続人が自己のために相続の開始があったことを知ったとき」について,相続の承認又は放棄をすることができる状態であること,すなわち,第一相続(*本件ではAの相続)が開始したことを知っていることを前提としていると読むべきであり,第一相続の相続人(*本件ではB)が自己のために第一相続が開始していることを知らずに死亡した場合は,民法916条はそもそも適用されず,第一相続の相続人としての地位を包括承継した再転相続人(*本件ではX1,X2)が,民法915条の規定に則り,第一相続についての承認又は放棄をすれば足りるとし,本件の場合,Aの相続(第一相続)に関するX2の熟慮期間は,X2が父BからAの相続人ついての地位を承継した事実を知った時から起算され,本件相続放棄は熟慮期間内にされたものとして有効となると判断しました(大阪高等裁判所・平成30年6月15日判決)。
今回は,Y社の上告について最高裁が示した判断を紹介します。
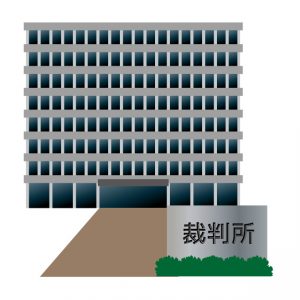
裁判所の判断
〇 熟慮期間の起算点である「自己のために相続の開始があったことを知った時」(民法915条)の解釈
相続人は,自己が被相続人の相続人となったことを知らなければ、当該被相続人からの相続について承認又は放棄のいずれかを選択することはできないのであるから,民法 915 条 1 項本文が熟慮期間の起算点として定める『自己のために相続の開始があったことを知った時』とは,原則として,相続人が相続開始の原因たる事実及びこれにより自己が相続人となった事実を知った時をいうものと解される(最高裁昭和57 年(オ)第82 号同 59 年 4 月 27 日第二小法廷判決・民集 38巻 6 号 698 頁参照)。
〇 再転相続人の熟慮期間を定めた民法916条の趣旨
民法 916 条の趣旨は,「BがAからの相続について承認又は放棄をしないで死亡したときには,BからAの相続人としての地位を承継したX2において,Aからの相続について承認又は放棄のいずれかを選択する ことになるという点に鑑みて,X2の認識に基づき,Aからの相続に係るX2の熟慮期間の起算点を定めることによって,X2に対し,Aからの相続について承認又は放棄のいずれかを選択する機会を保障すること」にあるのであり,「X2 のためにBからの相続が開始したことを知ったことをもって,Aからの相続に係る熟慮期間が起算されるとすることは,X2に対し,Aからの相続について承認又は放棄のいずれかを選択する機会を保障する民法 916 条の趣旨に反する。」
〇 民法916条の「その者の相続人が自己のために相続の開始があったことを知ったとき」の解釈
以上によれば,「民法 916 条にいう『その者の相続人が自己のために相続の開始があったことを知った時』とは,相続の承認又は放棄をしないで死亡した者の相続人が,当該死亡した者からの相続により,当該死亡した者が承認又は放棄をしなかった相続における相続人としての地位を,自己が承継した事実を知った時をいうものと解すべきである。」
なお,最高裁は,原審・大阪高裁が民法916条が適用される場面をBにおいて自己がAの相続人であることを知っていた場合に限定した点については,「Bにおいて自己がAの相続人であることを知っていたか否かにかかわらず民法 916 条が適用されることは,同条がその適用がある場 面につき,『相続人が相続の承認又は放棄をしな いで死亡したとき』とのみ規定していること及び 同条の前記趣旨から明らか」であるとして,原審の判断には民法 916 条の解釈適用を誤った違法があると指摘しています(本件の相続放棄が熟慮期間内にされたものとして有効との結論は是認)。

解 説
◇ 相続の承認,放棄と「熟慮期間」
人が亡くなると自動的に相続が開始します。相続とは亡くなった人(被相続人)の財産,権利・義務の一切を引き継ぐことを言い,財産にはプラスの財産だけではなくマイナスの財産 (負債)も含まれるので,負債を多く抱えていた人を必ず相続しなければならないとしてしまうと,相続人としては他人の死という自分ではコントロールできないことによって非常に酷な状態に置かれてしまうことになってしまいます。このため,民法は,相続人に相続を承認するか放棄するかの選択権を認めています。この相続を承認するか,それとも放棄するかを選択する期間について,民法915条1項は,「相続人は,自己のために相続の開始があったことを知った時から3箇月以内に,相続について,単純若しくは限定の承認又は放棄をしなければならない」と規定しています。この3ヶ月を相続の熟慮期間と言います。3ヵ月という短い期間ではどうしても選択できないという場合には,家庭裁判所の許可が必要になりますが,熟慮期間を伸長することも認められています(同項但書)。
熟慮期間の起算点は,条文では「自己のために相続の開始があったことを知った時」となっており(915条1項),最高裁判例においても,原則として,「相続人が相続開始の原因たる事実及びこれにより自己が相続人となった事実を知った時から起算すべきもの」とされています(本件判決が引用する最高裁第2小法廷昭和 59 年 4 月 27 日判決・民集 38巻 6 号 698頁)。ただ,この最高裁判例は,「相続人が右各事実を知った場合であっても,右各事実を知った時から 3 か月以内に限定承認又は相続放棄をしなかったのが,被相続人に相続財産 が全く存在しないと信じたためであり,かつ,被相続人の生活歴,被相続人と相続人との間の交際状態その他諸般の状況からみて当該相続人に対し相続財産の有無の調査を期待することが著しく困難な事情があって,相続人において右のように信ずるについて相当な理由が認められるとき」には,例外として,「相続人が相続財産の全部又は一部の存在を認識した時又は通常これを認識しうべき時」から起算するのが相当としています。亡くなった人に相続財産がないと信じることについて無理からぬ事情がある場合に限って,3ヶ月を徒過してしまっても,相続放棄の機会を認めている訳です。
◇ 「再転相続」とは?
本件では「再転相続(さいてんそうぞく)」が生じた場合の熟慮期間の起算点が問題となっています。「再転相続」とは,ある相続(一次相続)が開始した後,その相続人が相続の承認または放棄をしないまま死亡し,二次相続も開始したケースにおける二次相続の相続人による一次相続の相続のことをいいます。本件では,X1,X2らがAの相続についての再転相続人ということになります。
再転相続人からみると,承認または放棄の選択をする対象となる相続が2つ(第一相続と第二相続)あることになります。この点について,再転相続人の第一相続に関する選択権は第一相続の相続人から引き継がれるものではなく再転相続人の固有の権利であるとして,再転相続人は,第一相続,第二相続とも,順序に関係なく承認・放棄を自由にできるとする見解もありますが,最高裁昭和63年6月21日判決は,再転相続人は第一相続,第二相続のそれぞれについて承認・放棄を格別に選択することができるが,先に第二相続を放棄した場合には,再転相続人は第一相続の相続人の権利義務を何ら承継しなくなるとして,第一相続についての選択権も失うことになるとしています(この最高裁の考え方によれば,先に第一相続を承認し,後から第二相続を放棄することは可能ということになります)。
本件では,X1,X2らは,第二相続(Bの相続)について相続放棄の手続を採っていないので,第一相続(Aの相続)について承認・放棄の選択をすることは順序の点からは問題とはならず,3ヶ月の熟慮期間をどこから起算すべきかが争われました。
◇ 「再転相続」における第一相続の熟慮期間の起算点
再転相続が生じた場合の熟慮期間の起算点については,民法915条1項の特則として916条が設けられており,「相続人が相続の承認又は放棄をしないで死亡したときは,前条第1項の期間は,その者の相続人が自己のために相続の開始があったことを知った時から起算する」と規定されています。「その者の相続人」が再転相続人(本件のX2ら)を指すことは明らかですが,「自己のために相続の開始があったことを知った」という対象となるのは第二相続のことなのか,それとも第一相続のことなのかに争いがありました。
原審の大阪高裁は,前者の立場,すなわちX2が第二相続(Bの相続)の開始があったことを知った時から第一相続の熟慮期間も原則として起算されるとした上で,例外として,第一相続の相続人(B)が第一相続の相続人となったことを知らずに死亡した場合には916条は適用されず,915条の規定に則り,「自己のために相続の開始があったことを知った時」から第一相続の熟慮期間を起算すればよいと判断しました。第二相続の開始を知った時から第一相続の熟慮期間も起算されるという見解は,実は従前の通説的見解であったようです。しかし,この見解に立つと,本件のように第一相続の被相続人Aとの関係が疎遠な人が再転相続人となるケースにおいては,再転相続人が全く予想できない形で負債を相続してしまうリスクも出てきます。原審の大阪高裁判決は,こうした不都合を916条の適用場面を限定することによって解消しようとした訳ですが,本最高裁判決は,第一相続の相続人が第一相続の相続人となったことを知っていた場合に916条の適用場面を限定するという解釈は条文の文言及び916条の規定の趣旨から取り得ないと大阪高裁の見解を退けた上で,再転相続人(X2)が「当該死亡した者(=B)からの相続により,当該死亡した者が承認又は放棄をしなかった相続(=Aの相続)における相続人としての地位を,自己が承継した事実を知った時」を熟慮期間の起算点とすることにより,再転相続人の選択の機会を保障したのです。
 コメント
コメント
本判決は再転相続における熟慮期間の起算点を規定する民法916条の解釈を示した初めての最高裁判決として注目されました。核家族化,そして少子化が進展している現代では,疎遠になっている親族の相続人となるケースは決して珍しくないと思われます。その場合,債務を抱えていた人の相続人となったことを知った時から3ヵ月の熟慮期間が起算され,その間に相続放棄をすれば債務を引き継がなくてすむことが今回の判決により明確になりました。今後の債権回収の実務等にも影響があるものと思います。

 事案の概要
事案の概要


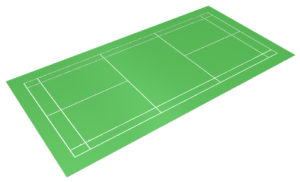
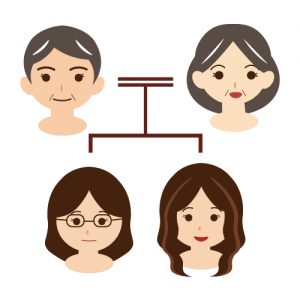 事案の概要
事案の概要

 事案の概要
事案の概要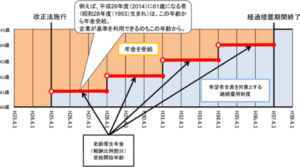
 【事案の内容】
【事案の内容】 【裁判所の判断】
【裁判所の判断】